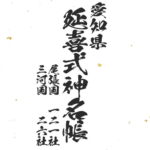神社情報
| 神社名 | 灰寶神社 |
| 鎮座地 | 愛知県豊田市越戸町松葉52 |
| 御祭神 | 速邇夜須毘売命 |
| 創 建 | 慶雲三年(706年) |
| 社格等 | 郷社 |
| 神名帳 | 延喜式神名帳:三河国加茂郡 灰寶神社 三河国神名帳:賀茂郡正五位下 灰寶天神 |
| 文化財 | ー |
| 例大祭 | 十月第二日曜日 |
| 境内社 | 山ノ神神社 津島神社 御尺口神社 産森ノ神社 越戸神社 秋葉神社 |
| URL | ー |
| 御朱印 | ー |
| 参拝日:2021年11月4日 |
御由緒
創建は社殿によると慶雲三年(706年)正月であると伝えられています。
ここ灰寶神社は、延喜式神名帳に「参河国加茂郡 灰寶神社」として記載されている式内社の論社の一社となります。
現在、矢作川に架かっている「平戸橋」近くにある「渡岩弁天」を灰寶神社であるという説がある。またこの地に住む人たちを「越人」と書き、灰寶神社の音に近かったとし、明治元年挙母藩で式内と定め社号灰寶としたとしています。
・・・ということは、江戸時代には別の社名だったのでしょうか?
この伝承で出てくる渡岩弁天の近くに神社が鎮座しており、この神社の社名を「胸形社」になります。また、矢作川の対岸には「馬場瀬神社」が鎮座しているのですが、この胸形社と馬場瀬神明社も灰寶神社の論社となっています。灰寶神社、胸形社、馬場瀬神社の三社の位置関係は矢作川に沿って鎮座していて大凡一キロほどの距離に固まっています。また、馬場瀬神社が鎮座する場所には馬場瀬古墳群があり、往古よりこの辺りを支配していた豪族の中心でだったと考える事ができそうです。
- 延喜元年(905年)、延喜式神名帳に「三河国加茂郡 灰寶神社」と記載。
- 時期不詳、三河国神名帳に「加茂郡正五位下 灰寶天神」と記載。
- 永延二年(988年)四月、原信之進平氏勝、社殿再建。
- 久安五年(1148年)十一月、永井九十郎之勝、再建。
- 正応三年(1290年)八月、原田勝之介信里、再建。
- 応永七年(1400年)正月、畠山某、再建
- 永禄十二年(1569年)、本多時之介忠勝、再建
- 明治五年十月十二日、村社に列格。
- 明治四十五年十月二十六日、神饌幣帛料供進指定社となる。
- 昭和六年十月二十六日、郷社に昇格。
- 昭和七年十一月十七日、社殿改築。
灰寶神社の御祭神は?
灰寶神社の御祭神は「速邇夜須毘売命」で、別の神名は「埴安神」であるとしています。そうなると、神名の「速」は「波」の誤植である可能性もありそうです。
土の神であり土器の神でもあるとされている「ハニヤス」は、古事記・日本書記共に伊邪那岐命と伊邪那美命による神生みの中、火の神である「火之加具土命」を生んだ際、陰部を焼かれた伊邪那美命がもがき苦しんでいる間、糞より成った神になります。日本書記では土の神とも記されており、古墳時代に埴輪や土器などの製造を取り仕切っていた「土師部」と呼ばれる人々の崇敬を集めていた神になるそうです。
埴安神とは?
埴安神とは日本書記で書かれている神名で、古事記では 波邇夜須毘古神と波邇夜須毘売神と男神女神一対の神として書かれています。この埴安神は、伊邪那岐命と伊邪那美命による「神生み」の中で出現する神となっています。
埴安神の神名に使われている”埴”とは「きめの細かい、黄赤色の粘土」を意味しており、これは古代の縄文土器や弥生土器などの原料となる土を指す事から、土の神、焼き物(陶器)の神として崇敬を集める神になります。土の神から転じて、田圃の畔や川の堤などの守護神としても祀られる事があるようです。
灰寶神社とは矢作川の対岸に位置する場所に「馬場瀬古墳群」があって八基の古墳が確認されています。この古墳の装飾や埋葬に使った埴輪や土器などを製造する土師部たちは土の神である「ハニヤス」をこの地に祀ったのかもしれませんね。
延喜式内社巡りin三河国
新型コロナウィルスパンデミックの早期沈静化を祈願する為に、まずは三河国内にある式内社を参拝して廻ろうかとおもっています。自分の神社巡りは、基本バイクを使って一人で巡って行くので、密にならず、ソーシャルディスタンスも確保し、さらに喋らないという感染防止策は万全の状態を維持しやすいかなと思っています。そこで、感染状況が改善しつつある時期を見極めながら参拝していき、その模様を紹介できたらと思います。
- 加茂郡 七座(6/7)
- 額田郡 二座(2/2)
- 稲前神社 岡崎市稲熊町鎮座
- 碧海郡 六座(6/6)
- 幡豆郡 三座(3/3)
- 宝飯郡 六座(5/6)
- 八名郡 一座(1/1)
- 渥美郡 一座(1/1)
- 阿志神社 田原市芦町鎮座
- 合 計 二十六座(23/26)
参拝記
現在は矢作川に沿うような感じでバイパスともいえる新道が敷設されている為、国道153号線はその新道に付け替えられて、県道に変わりそうな感じがしますが、2021年現在はまだ国道153号線沿いに灰寶神社は鎮座しています。神社のすぐ隣は越戸子ども園になっているので、この子ども園を目印にしてもいいかもしれませんね。
境内入口

社殿正面の境内入口になります。こちらには社号標と石灯篭一対と扁額が掲げられた明神鳥居が据えられています。

社号標は旧社格が彫られていないすっきりした様式の物が据えられています。彫られている文字が特徴的だなと思って社号標を眺めていると・・・

こちらの社号標は海軍元帥東郷平八郎による書体でした。日露戦争における日本海海戦の完勝もあって当時の日本では東郷元帥の人気?はすごかったのかもしれませんね。
もう一つの境内入口

灰寶神社には、もう一つ鳥居と社号標が据えられている境内入口が設けられています。社号標を見る限り、郷社に昇格する以前に使われていた物で、「村社 式内 灰寶神社」と彫られています。
手水舎
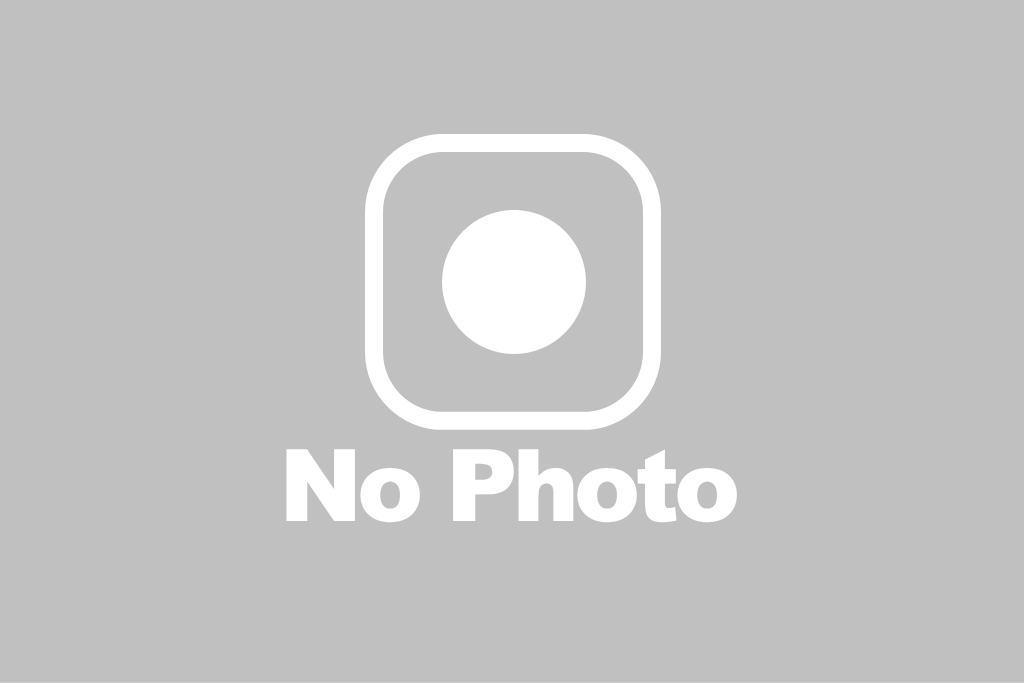
コンクリート造瓦葺四本柱タイプの手水舎になるのですが、思いっきり写真を撮影し忘れていました・・・。
狛犬

開放型拝殿の前に鎮座する昭和五年生まれの狛犬一対になります。
灰寶神社にはもう一対の狛犬が神門前に鎮座しています。

昭和五十二年生まれの陶器製の狛犬一対になります。陶器製という事で石造りと比べても装飾が細かく、非常に表情豊かな狛犬になっているかと思います。やはり、御祭神が速邇夜須毘売命(埴安神)という事で、土器(陶器)製の狛犬が寄進されたという事でしょうか。
社殿

灰寶神社の社殿は切妻造銅板葺妻入りの開放型の拝殿(または絵馬殿)、その後方には石造りの瑞垣内に四方殿(舞殿)、そして神門と透塀で囲まれた流造の本殿が鎮座する当サイトでは”豊田式”と呼んでいる社殿配置になっています。

社殿を正面から望みます。拝殿、四方殿、神門の真ん中を正中が通っていて、本殿と直線で結ばれている事がここからみるとよくわかって頂けるかと思います。

拝殿と神門の間に設けられているコンクリート造りの四方殿になります。サイズ的には舞殿または神楽殿として使用されているのではないかと思われます。

そして、こちらが神門と袖壁となる透塀、そして土塀による瑞垣で囲まれている本殿になります。神門と本殿の間には祭殿または祝詞殿と呼んでいいかと思いますが、祭祀の際、宮司以下祭員の座が設けられると思われるこれまた開放型の建物が設けられています。
境内社

本殿向かって右側に鎮座している境内社の相殿になります。この相殿の裏側に産森ノ神社が鎮座しています。

英霊の御魂を祀っている「越戸神社」です。カーポートの様な鞘堂が特徴的ですね。
宝物庫

こちらのコンクリート造りの蔵は、太平洋戦争時に名古屋から文化財を被害から守るために文化財の疎開が行われ、数多くの文化財が運び込まれたという歴史を持っています。名古屋城本丸御殿の襖などもここに逃れていた為焼失を免れています。
地図で鎮座地を確認
| 神社名 | 灰寶神社 |
| 鎮座地 | 愛知県豊田市越戸町松葉52 |
| 最寄駅 | 名古屋鉄道三河線「越戸駅」徒歩7分 |
伊勢神宮、氏神の神社、そして皆様が崇敬している神社の御神札をご自宅にお祀りされていますか?
現在ではアパートなどの賃貸住宅でも気軽に御神札を祀る事ができる神棚が登場しています。今まで賃貸住宅で神棚が置けないと御神札をお祀りできなかった方も、こうした神棚をご用意されてお祀りされてみてはいかがでしょうか?