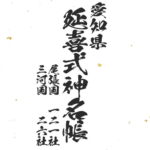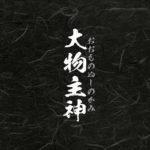神社情報
| 神社名 | 兵主神社 |
| 鎮座地 | 愛知県豊田市荒井町松島二九九番地一 |
| 御祭神 | 大物主命 大己貴命 三穂津姫命 天照大御神 大山祇命 建速須佐之男命 豊受皇大神 |
| 創 建 | 崇神天皇の御代 |
| 社格等 | 郷社 |
| 神名帳 | 延喜式神名帳:三河国加茂郡 兵主神社 三河国神名帳:加茂郡正五位下 兵主天神 |
| 文化財 | ー |
| 例大祭 | 十月十日 |
| 境内社 | ー |
| URL | ー |
| 御朱印 | ー |
| 参拝日:2021年11月2日 |
御由緒
社伝によると創建は第十代崇神天皇の御代としています。学術的にほぼ実在が比定されている第二代綏靖天皇から第九代開化天皇は「欠史八代」と呼ばれていて、比較的実在性があると考えられているのは第十代崇神天皇からだと言われています。
記紀に記されている年代をそのまま西暦に換算すると紀元前97年から紀元前30年の67年間が崇神天皇の御代になります。ただ、現実的に考えると、三世紀前後になるそうです。それでも兵主神社の創建は201年から300年の間という事になり、かなりの古社であるという事になります。
さらに社伝によると、大己貴命の十一代孫にあたる賀茂氏の君「大鴨積命」がこの地に滞在した際に祖神を祀ったという。そして、この地に出雲神社を模して階を作った事から、この地を高橋と称するようになった。賀茂の君が居した事から賀茂の郡→加茂郡、兵主は器主が変化したものとしています。
- 延喜元年(905年)、延喜式神名帳に「三河国加茂郡 兵主神社」と記載。
- 時期不詳、三河国神名帳に「賀茂郡正五位下 兵主天神」と記載
- 時期不詳、大島から現在の境内地に遷座(扁額に「大島大明神」とあり。)
- 明治元年(1867年)、挙母藩より式内社と定め、社号を「兵主神社」に改称。
- 明治五年(1871年)、郷社に列格
- 明治四十年(1907年)、神饌幣帛料供進指定を受ける
- 明治四十三年(1910年)、山神社、津嶋社、金比羅社、大神宮を合祀
- 大正五年(1916年)、神明社、宝田社、津嶋社を合祀
兵主神社の御祭神は?
兵主神社の主祭神は、戦前に記された「西加茂郡誌」、「明治神社誌料」共に、
- 大物主神
- 三穂都姫命
の二柱であるとしています。
明治、大正年間に神社統合策によって合祀した神社の御祭神五柱を配祀神としています。
- 大己貴命
- 天照大御神
- 大山祇命
- 建速須佐之男命
- 豊受皇大神
神社合祀
- 明治四十二年(1910年)
- 山神社(御祭神:大山祇命)を合祀
- 境内社:津島社(御祭神:建速須佐之男命)
金比羅社(御祭神:大己貴命?)
大神宮(御祭神:天照大御神?)
- 境内社:津島社(御祭神:建速須佐之男命)
- 山神社(御祭神:大山祇命)を合祀
- 大正五年(1916年)
- 神明社(御祭神:天照大御神)を合祀
- 宝田社(御祭神:豊受皇大神?)
津嶋社(御祭神:建速須佐之男命)
- 宝田社(御祭神:豊受皇大神?)
- 神明社(御祭神:天照大御神)を合祀
上記七社をそれぞれ本殿に合祀。
大物主命と大己貴命
「大己貴命」は、出雲系神話の最高神と位置付けられている神である「大国主神」の別称として日本書紀に記されている神名になります、古事記では「大国主神」と記しているのに対し、日本書紀では殆どを別称とする「大己貴命」と記しているのが特徴です。
そして、大国主神の国作りで欠かす事ができない「大物主命」についても記紀では大きな違いがあります。「古事記」では大物主命と大国主命は別神としているのに対し、「日本書紀」では大国主神の別称が大物主神であるとしています。さらに、大神神社の御神体である三輪山に鎮座している大物主神は大己貴神の和魂であるとするなど、大己貴命と大物主神は同一神としています。
ここ兵主神社の御祭神の名前を見ていくと、大物主命と大己貴命の神名が記載されています。大己貴命の神名は日本書記に登場する神名であり、大物主命とは同一神としている訳ですから、大物主命と大己貴命を合わせて一柱で表記すればいいのではと思うのですが、古事記では大国主神と大物主命は別神であるとしていることもあってそれぞれの神名が併記されているのかな。
ここで一つ疑問が・・・。
兵主神社の主祭神とする「大物主命」はいつ主祭神として祀られたのか。社伝によると、大己貴命の十一代孫にあたる賀茂氏の君「大鴨積命」がこの地に滞在した際に祖神を祀ったのが創建であるといる事から、「大己貴命を主祭神として創建した。」と考えてしまいそうですが、もう一方の三穂都姫命は、日本書紀には「高皇産霊尊の娘であり大物主神の后である。」と書かれている所から、創建当初から大物主命が主祭神だったと考える事もできそうです。
江戸時代に記された三河國官社考集説では主祭神を大物主命、相殿に三穂都姫命を祀るとしている所からも古くから大物主を主祭神としていたことが解ってきます。
なぜ、こんな疑問を持ったのか・・・。
それは、大己貴命はいつ御祭神として祀られたのか?
金毘羅社の本宮は香川県の金刀比羅社になり、江戸時代までは神仏習合が色濃い金毘羅大権現を主祭神としてきた神社になります。明治政府による神仏分離令によって金刀比羅社は「大物主命」を主祭神とする神社へと組織変更が行われていきます。当然、全国に鎮座する金刀比羅社も神社化が行われて、その大半が「大物主命」を主祭神とする神社へと変わっていきます。
全国に鎮座する金比羅社の大半が大物主命を主祭神とするなか、明治四十二年に兵主神社に合祀された金比羅社の御祭神は大己貴命であったと考えるのが一番可能性はありそうなのですが、今一釈然としません・・・。何か納得できる資料が見つかるといいんですが・・・。
延喜式内社巡りin三河国
新型コロナウィルスパンデミックの早期沈静化を祈願する為に、まずは三河国内にある式内社を参拝して廻ろうかとおもっています。自分の神社巡りは、基本バイクを使って一人で巡って行くので、密にならず、ソーシャルディスタンスも確保し、さらに喋らないという感染防止策は万全の状態を維持しやすいかなと思っています。そこで、感染状況が改善しつつある時期を見極めながら参拝していき、その模様を紹介できたらと思います。
- 加茂郡 七座(6/7)
- 額田郡 二座(2/2)
- 稲前神社 岡崎市稲熊町鎮座
- 碧海郡 六座(6/6)
- 幡豆郡 三座(3/3)
- 宝飯郡 六座(5/6)
- 八名郡 一座(1/1)
- 渥美郡 一座(1/1)
- 阿志神社 田原市芦町鎮座
- 合 計 二十六座(23/26)
参拝記
豊田市街地を南北に流れる矢作川の右岸側の堤防道路を南から走っていくと途中で国道153号線と合流して、そのまま平戸橋方面に抜けていけるのですが、その途中の篭川を渡河する荒井橋を渡った先に兵主神社が鎮座しています。
社務所の脇に1台分くらい車を停める場所があるのですが、始めて兵主神社を参拝しようとした場合、駐車できる場所を見つけるのが大変かもしれませんね。
社号標

国道沿いに据えられている旧社格「郷社」と「式内」が合わせれ彫られた兵主神社の社号標です。
鳥居

扁額が掲げられた明神鳥居になります。国道から参拝する際ようになってこちらの鳥居が言わば正面玄関となっているかんじですね。ただ写真奥を見ると分かる様に、元々の境内入口の鳥居ではないようで・・・

社殿正面側にも鳥居が据えられています。こちらは近年建立された鳥居のようです。その手前には・・・

「本国官社 兵主神社」と彫られた社号標が据えられています。式内社の事を「官社」と呼ぶみたいですね。
手水舎

国道側の鳥居近くに設けられている木造瓦葺四本柱タイプの手水舎です。
この手水舎からぐるっと回って社殿正面側の鳥居に向かうのが現在の参道となっているようですね。
社殿

切妻造瓦葺妻入の開放型拝殿を有する”豊田式”の社殿になります。
この拝殿なんですが、所々に鉄製の枠が設置されていて耐震補強が行われています。斜めの支え柱と比べると当然こちらのほうが視覚的にも違和感を感じさせない造りなんですが、当然こちらのが費用がかかるのですべての神社が採用しにくい補強方法ですね。

拝殿の先には石垣で一段高くなった場所に本殿が鎮座しその周囲を神門と透塀による瑞垣囲んでいます。神門と本殿の間には祭殿または祝詞殿が設けられています。

豊田式の社殿の特徴は神門の前で参拝する様になっている点ですかね。
狛犬

生年月を調べ忘れましたが、その造形と口の周りの朱染具合から平成二十年代生まれの狛犬なんじゃないかとおもうのですが、もう少し古いかな?
参道には・・・

ここ兵主神社では拾う氏子の方達が少ないのか、参道一面に銀杏が落ちていました。参拝した日は11月上旬。銀杏拾いのラストスパート時期ですかね。
地図で鎮座地を確認
| 神社名 | 兵主神社 |
| 鎮座地 | 愛知県豊田市荒井町松島二九九番地一 |
| 最寄駅 | 名古屋鉄道 三河線「越戸駅」徒歩12分 |
伊勢神宮、氏神の神社、そして皆様が崇敬している神社の御神札をご自宅にお祀りされていますか?
現在ではアパートなどの賃貸住宅でも気軽に御神札を祀る事ができる神棚が登場しています。今まで賃貸住宅で神棚が置けないと御神札をお祀りできなかった方も、こうした神棚をご用意されてお祀りされてみてはいかがでしょうか?