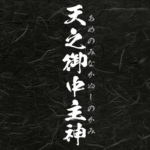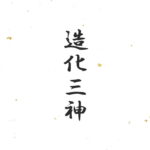神社情報
| 神社名 | 石座神社 |
| 鎮座地 | 愛知県新城市大宮字狐塚十四番地 |
| 御祭神 | 天之御中主神、天稚彦命 |
| 創 建 | 不詳 |
| 社格等 | 県社 |
| 神名帳 | 延喜式神名帳:三河国宝飯郡 石座神社 三河国神名帳:設楽郡正三位 磐倉大明神 |
| 文化財 | 国 宝:ー 国指定:ー 県指定:ー 市指定:木製神馬 |
| 例大祭 | 十月第二日曜日 |
| 境内社 | 児御前社(祭神:石鞍若御子天神) 須波南宮社(祭神:建南方刀美命) 荒波婆岐社(祭神:豊石窓命、希石窓命) 神楽社(宇須女命) 伊雑社(伊雑大神) 保食社(倉稲魂命) 山神社(大山祇命) 水神社(速秋津姫命) 金比羅社(大物主命) 白山社(白山比咩命) 祖霊社(天児屋根命) 素盞嗚社(素盞嗚命) |
| URL | ー |
| 御朱印 | ー |
| 参拝日:2021年9月22日 |
御由緒
石座神社の創建は不詳。
社記や棟札などの資料が元亀・天正年間に行われた武田信玄・勝頼によって行われた三河侵攻の中で社殿が灰燼に帰してしまい焼失してしまったと伝えられています。
岩座神社の本殿の裏手にある 雁峯山 (現在は石座神社と雁峯山の間には第二東名道路が建設され、風景が一変してしまっています。)には、複数の岩で構成されている磐座が存在し、大古より雁峯山を御神体とする祭場が設けられており、この磐座を祀る社として創建されたのが岩座神社であるとしています。社名である石座も「いわくら」と読み、磐座から名付けられた社名であることは間違いない様です。
延喜式が編纂される以前に書かれた書物にも石座神社は記されていて、この時点で神位が与えられています。
「文徳實録」仁寿元年(851年)・・・石鞍神 従五位下
「三代實録」元慶七年(883年)・・・石鞍神 従五位上
平安時代初期より栄えていた神社であることを示しているかと思います。
最初に戻りますが、戦国時代に社殿が焼失してしまった際に資料なども失ったとされ、いつどういった神を祀って創建され、どういった歴史を辿ってきたのかという事はすべて不詳となってしまっています。ただ、この近くで設楽原の合戦が行われている事から、織田・徳川連合軍の戦勝祈願が行われたのではないかなと想像しています。
石座神社の御祭神は?
石座神社の御祭神は「天之御中主尊」、「天稚彦命」であると伝えられています。
もう一柱の「天稚彦命」は古事記の中で「天上の神に反逆したために返し矢に当たって死んでしまう」という神として描かれている事もあり、祭神として祀っている神社は非常に少なく、石座神社もその数少ない神社の一社になります。
大正五年三月には、石座神社近隣に鎮座していた神社を本殿に合祀しています。
- 無格社 山住社(祭神:大山祇命)
- 無格社 厳島社(祭神:比売命)
- 無格社 青木社(祭神:倉稲總命)
- 無格社 熊野社天王社(祭神:素戔嗚尊)
- 無格社 白山社(祭神:伊邪那美命)
延喜式内社巡りin三河国
新型コロナウィルスパンデミックの早期沈静化を祈願する為に、まずは三河国内にある式内社を参拝して廻ろうかとおもっています。自分の神社巡りは、基本バイクを使って一人で巡って行くので、密にならず、ソーシャルディスタンスも確保し、さらに喋らないという感染防止策は万全の状態を維持しやすいかなと思っています。そこで、感染状況が改善しつつある時期を見極めながら参拝していき、その模様を紹介できたらと思います。
- 加茂郡 七座(6/7)
- 額田郡 二座(2/2)
- 稲前神社 岡崎市稲熊町鎮座
- 碧海郡 六座(6/6)
- 幡豆郡 三座(3/3)
- 宝飯郡 六座(5/6)
- 八名郡 一座(1/1)
- 渥美郡 一座(1/1)
- 阿志神社 田原市芦町鎮座
- 合 計 二十六座(23/26)
参拝記
国道151号線「大宮交差点」を豊川方面からだと左折して道なりに1.2km程進むと、今回紹介する「石座神社」の参道が見えてきます。岩座神社が鎮座する辺りは、織田信長・徳川家康連合軍と武田勝頼軍が激突した「設楽原古戦場」のまさに織田・徳川方に布陣場所近くに鎮座しています。国道151号線から岩座神社に向かう途中にも、徳川家康本陣跡となる八剣神社の脇を通過していたりします。石座神社への参拝の際には、設楽原古戦場巡りや、少し足を延ばして「長篠城」周辺を散策される事をお勧めします。この戦いで有名な馬防柵が再現されていたり、設楽原歴史資料館では数多くの火縄銃に触れる事ができます。
設楽原歴史資料館についてはこちらから
実は、石座神社の参道はJR飯田線の茶臼山駅近くにある県道439号線の「茶臼山駅入口交差点」の角に石座神社参道の石柱が建てられています。この県道439号線が古くからの街道筋でこの街道から石座神社へつながる参道入口が繋がっていたという事でしょうね。直線距離で2kmも離れた場所に参道入口が設けられているという事から古くから信仰を集めていた神社であるということがこの辺りからも伺えますね。
境内入口

石座神社の後方?には第二東名高速道路の高架が望むことが出来る場所に石座神社の境内入口となる石段が設けられています。丁度T字交差点の角部分になっているので、国道方面から進んできた場合は非常にわかりやすいのではないでしょうか。
社号標

旧社格「県社」と延喜式内社を示す「式内」が彫られた石座神社の社号標になります。
一之鳥居

建立年月は調べ忘れてしまいましたが、扁額が掲げられた明神鳥居の一の鳥居になります。
二之鳥居

一の鳥居から森の中を通るコンクリート敷きの参道が続いていて、進んでいくと、扁額が掲げられた二の鳥居が見えてきます。二の鳥居の先から広く切り開かれた境内が続いています。
手水舎

木造瓦葺四本柱タイプの手水舎になります。水盤と井戸が据えられている様式の手水舎となっていて、それぞれの柱間が広くとられているのが特徴的な手水舎になります。
狛犬

大正十一年生まれの狛犬一対になります。台座部分などに山間にある神社によくあるのですが、苔が生えていて独特の雰囲気を醸し出しています。
社殿

入母屋造銅板葺平入の入母屋破風の向拝と高覧のある濡れ縁が設けられた拝殿を有する社殿になります。

本殿は拝殿から一段高くなった場所に鎮座しており、流造となっています。拝殿から斜めに渡殿が伸びていて、その先にある妻入りの建物は祝詞殿かな。
境内社

社殿向かって左手に鎮座する境内社の相殿(山神社、保食社、伊雑社、神楽社)

社殿向かって右側に鎮座する摂社となる児御前社になります。

さらに、境内社の相殿( 水神社、金比羅社、白山社、祖霊社 )と石造りの社、宝篋印塔などがあります。

摂社である須波南宮社と末社である天王社(説明板では素戔嗚社)の社は参道から少し山を登った先に鎮座しています。

二之鳥居のすぐ脇に鎮座する荒波婆岐社になります。
射場

石座神社の境内には、大祭などで行われているのであろう弓道の射場が設けられていまっした。射場がある神社は拝殿の横とか絵馬殿などに「金的中」などが書かれた扁額が掲げられていたりしますね。案外射場がある神社って多いですね。
木造神馬

境内の一角には、新城市の指定文化財となっている木造神馬とその鞘堂が建っています。

元々は白い馬の像だったのが、夜な夜な逃げ出して農作物を食べてしまう為、黒く塗ってしまうと逃げ出さなくなったという逸話がある神馬なんだそうです、たしかに所々黒い塗料が残っていますね。
地図で鎮座地を確認
| 神社名 | 石座神社 |
| 鎮座地 | 愛知県新城市大宮字狐塚十四番地 |
| 最寄駅 | 豊鉄バス「新城富永バス停」徒歩20分 |
伊勢神宮、氏神の神社、そして皆様が崇敬している神社の御神札をご自宅にお祀りされていますか?
現在ではアパートなどの賃貸住宅でも気軽に御神札を祀る事ができる神棚が登場しています。今まで賃貸住宅で神棚が置けないと御神札をお祀りできなかった方も、こうした神棚をご用意されてお祀りされてみてはいかがでしょうか?