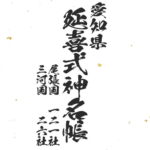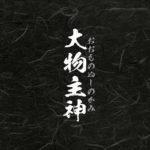神社情報
| 神社名 | 御津神社 |
| 鎮座地 | 愛知県豊川市御津町広石祓田七十番地 |
| 御祭神 | 大国主命 事代主命 健御名方命 |
| 創 建 | 不詳 |
| 社格等 | 縣社 |
| 神名帳 | 延喜式神名帳:三河国宝飯郡 御津神社 三河国神名帳:宝飯郡正三位 御津大明神 |
| 文化財 | 国 宝: 国指定: 県指定: 市指定:大般若経、半鐘、鰐口三点、クスノキ、舟山古墳 |
| 例大祭 | 四月第三日曜日 |
| 境内社 | 荷神社 天満宮 祖霊社 磯宮神社 御鍬神社 秋葉神社 富野御前神社 八幡社 船津神社 天地万神神社 招魂社 |
| URL | ー |
| 御朱印 | ー |
| 参拝日:2022年10月4日 |
御由緒
- 創建年代は不詳
伝承では、御津神社の御祭神は伊勢より船に乗り、御舳玉・磯宮楫取・船津各大神等の随従でこの地にたどり着いたといいます。ちなみに、この御船が着いた所を「船津」と云うそうです。
随従した三柱の神々とは
- 御舳玉大神
住吉大神と同一視されており、御津神社から北東に位置する豊川市御津町豊沢石堂野十五番地に鎮座する御舳玉神社にて祀られています。
- 磯宮楫取大神
綿津見命と同一視されており、御津神社の境内摂社「磯宮宮」の御祭神として祀られています。
- 船津大神
猿田彦神と同一視されており、御津神社の境内摂社「船津社」の御祭神として祀られています。
宝飯郡には「大国主命」を主祭神とする神社が多く創建されており、出雲族と呼ばれる一族が出雲よりこの地に移り住んだのではないかと思われます。そしてこの出雲族の先道役を担っていたのが航海術に長け、さらに住吉神社の神職も務めていた「津守氏」だったのではないかと見られ、出雲族が大国主命(大己貴尊)を主祭神とする神社を創建し、津守氏は住吉大神を主祭神とする神社を創建しながら、御津地区から徐々に内陸にその勢力を広げていったと考えられます。東三河でこの出雲族や津守氏が建立した神社で一番有名?なのは延喜式内社であり三河国一之宮とされる「砥鹿神社」とその境外摂社である「津守神社」になるのではないでしょうか。
- 第八代孝元天皇の御代、天皇が当国行幸の時に御船を此津に寄せられたことから、この地を「御津湊」と称するようになり、社号を御津神社とした。
- 天武天皇四年(675年)、圭田五十六束所を奉納された。
- 「日本惣国風土記」第六十九:三河国宝飯郡御津神社、圭田五十六束所、祭下照比咩也、天武天皇四年乙亥二月始奉圭田加神禮
- 仁寿元年(851年)十月、文徳実録に「従五位下」を授かると記載。
- 延喜元年(905年)、延喜式神名帳に「三河国宝飯郡 御津神社」と記載。
- 時期不詳、三河国神名帳に「宝飯郡正三位 御津大明神」と記載。
領主からの寄進
御津神社に残されている棟札などから、室町時代以降、この地の領主より崇敬を集めいたようです。
- 一色義範:応永七年(1400年)~永享十二年(1440年)
- 応永二十二年(1415年)、社殿再建
- 永享十一年(1439年)、社殿屋根葺き替え
- 細川兵部少輔(勝久か?):生没不詳
- 享徳元年(1452年)、洪鐘を寄進
- 牧野保成(不詳~永禄六年(1563年)
- 天文十五年(1546年)、社殿屋根葺き替え
- 明治五年(1872年)、郷社列格
- 明治十五年(1882年)、縣社昇格
- 明治四十年(1907年)、神饌幣帛料供進神社に指定される。
御津神社の御祭神は?
愛知県神社名鑑では御津神社の御祭神を
- 大国主命
- 事代主命
- 健御名方命
の三柱であるとしていますが、社頭の由緒書きなどでは、大国主命の一柱のみを御祭神としています。
この三柱の神は、出雲神話の主人公ともいえる「大国主命」とその子「事代主命」「建御名方命」であることから、まさに出雲族がこの地にやってきた時に、守護神として勧請したのでしょう。
では、何時頃出雲族がこの地にやってきたのでしょうか。
当サイトでは、景行天皇の御代、それまで尾張国周辺を東端としていたヤマト朝廷の勢力圏が日本武尊の東征によって一気に関東の方までその勢力を伸ばす事に成功しています。その後、持統天皇の三河行幸直前に勅命で「砥鹿神社(大宝元年間(701-04年))」が建立されている事から少なくとも飛鳥時代にはこの地に出雲族が移り住んでいると考えられます。
大国主命
大国主命は古事記では「大国主神」、日本書紀では「大己貴命」で登場する神になります。また、日本書紀では「大物主神」は大国主の幸魂、奇魂であるとしており、同一神であるしており、別神として書かれている古事記とは異なる描写もされています。
大国主神は豊葦原中つ国の国作りを成した「国津神」の最高神として描かれており、国譲りとして天照大御神率いる天津神が住む高天原に従属した後は、出雲大社の御祭神として鎮まったとされています。
事代主命
古事記、日本書紀共に「事代主命」として登場する神になります。
中つ国の国譲りの時、天照大御神は経津主神・武甕槌神を派遣させると、大国主神は二人の息子が承諾するのなら国を譲りましょうと返答をしたので、武甕槌神は事代主命の元に向かい国譲りを迫ると「承知した。」というと青柴垣の中に隠れてしまった。
事代主命は島根県松江市に鎮座する「美保神社」の御祭神として祀られています。
建御名方命
日本書紀では「武甕槌神」、古事記では「建御雷之男神」として登場する神になります。
大国主の息子として中つ国国譲りの時に、事代主命とは異なり国譲りに反対する姿勢を見せ、武甕槌神と力比べを申し出るが、やすやすと放り投げられ、科野国の州羽海まで追いつめられた時、この地から出ず、国譲りにも賛同する事を条件に許されたという。
建御名方命は上記の通り諏訪の地から出ないという約束の通り「諏訪大社」の御祭神として祀られています。
建速須佐之男命 ━ 須勢理毘売命
┃
大国主命 ━ 建御名方命
┣ 事代主命
神屋楯比売命
建御名方命は、大国主命の御子とは記載があるが母については記載なし。
天武天皇四乙亥年(675年)二月、圭田を奉る。仁寿元年(851年)十月、従五位下となる。
愛知県神社庁発刊「愛知県神社名鑑」より
「延喜式神名帳」に国幣小社に列し、「三河国内神明帳」に正三拉御津大明神とある。応永二十二年(1415年)源義範社殿を再建し、永亨十一年(1439年)には屋根葺替を行う。享徳元年(1452年)十月、細川兵部少輔は洪鐘を奉納する。天文十五年(1546年)牛久保城主牧野保成屋根葺替る。明治五年四月十六日、郷社に列し、同十四年十二月、有栖川宮熾仁親王より神号染筆を奉る。同十五年五月二十八日、県社に昇格する。同四十年十月二十六日、供進指定となる。第八代孝元天皇三河国に行幸の際この地に着く御津と云う。住吉御津七郷十ニヶ対の総氏神で、明治五年更に六ヶ村を加え十八ヶ村の崇敬をあつめた、中古は社領七十五石と伝え、祓田、祢宜田、神子田、の字名を残す。
延喜式内社巡りin三河国
新型コロナウィルスパンデミックの早期沈静化を祈願する為に、まずは三河国内にある式内社を参拝して廻ろうかとおもっています。自分の神社巡りは、基本バイクを使って一人で巡って行くので、密にならず、ソーシャルディスタンスも確保し、さらに喋らないという感染防止策は万全の状態を維持しやすいかなと思っています。そこで、感染状況が改善しつつある時期を見極めながら参拝していき、その模様を紹介できたらと思います。
- 加茂郡 七座(6/7)
- 額田郡 二座(2/2)
- 稲前神社 岡崎市稲熊町鎮座
- 碧海郡 六座(6/6)
- 幡豆郡 三座(3/3)
- 宝飯郡 六座(5/6)
- 八名郡 一座(1/1)
- 渥美郡 一座(1/1)
- 阿志神社 田原市芦町鎮座
- 合 計 二十六座(23/26)
参拝記
豊川市役所御津支所(御津町役場跡)から北西に進み、御津川沿いを走ると御津神社の境内入口から真っ直ぐまるで参道の様に伸びている市道との三差路になります。御津川と渡河して正面に鳥居が見える市道を進めば御津神社になります。
駐車場は脇参道から境内の一角に駐車する形になるかと思うのですが、非常にわかりにくいので注意してください。
大恩寺と御津神社
御津神社の境内入口脇には、徳川氏に所縁のある浄土宗御津山大恩寺が建っています。こちら大恩寺と御津神社の間には御津地区に伝わる伝承があるそうで・・・・。
大恩寺は、御津神社の神様が大恩寺の鐘がききたいから近くにこいといわれたので、御津神社のそばに移ってきたが、それ以来住職は御津神社の例祭の宵祭りの日に参拝して、阿弥陀経をあげることになっていた。
大恩寺の開基は安祥松平氏初代「松平忠親」、最初新宮山に創建されたが、その後御津山に移された。浄土宗の本山である知恩院の二十二世珠琳、二十三世愚底、二十四世訓公、二十五世存牛を輩出するなど室町時代中期の浄土宗を支える寺院であったと言えるかと思います。言い換えれば、浄土宗の本山である知恩院に対してこれだけの影響力を与えた松平氏の浄土宗への庇護がずば抜けていた証左なのではないかと思われます。
こうした伝承があるのですが、大恩寺が御津神社の別当だったのかは不明です。
境内入口

御津神社の境内入口は、幟ポールと石造の明神鳥居と社号標が据えられています。

写真を撮影している場所から左を向くと、建物の向う側には大恩寺の重層の山門が見えています。
鳥居・社号標

扁額が掲げられた石造り明神鳥居の一の鳥居と木に遮られてしまいよく分からないかと思いますが、「式内 御津神社」と彫られた社号標になります。

一の鳥居を潜って境内に向かってコンクリート造りの参道が伸びています。

扁額が掲げられた木造の明神鳥居と、「縣社式内御津神社」と彫られた社号標になります。
鳥居は、根元を見ると石造りの基礎部分に接ぎ木の様な形で鳥居本体部分を接続していて、今設置されている鳥居はもしかしたら二代目かな?
手水舎・水盤

木造瓦葺四本柱タイプの手水舎です。水盤の大きさと比べても非常にコンパクトな造りな事がみてとれますね。
狛犬

明治四十年生まれの狛犬一対になります。
社殿

切妻造瓦葺妻入りの高覧のある濡れ縁が設けられた拝殿を有する社殿になります。
流造の本殿が鎮座しているのですが、本殿の周囲がトタン波板が囲まれてしまっていて少し味気ない感じですね。
境内社

摂社「船津神社」 
摂社「磯宮神社」
境内には、御祭神を随従した御舳玉大神・磯宮楫取大神を祀った境内社が鎮座しています。元々は別の場所に鎮座していたそうなのですが明治時代になり御津神社の境内に遷座、境内社となったようです。

秋葉社と鈴宮社 
御鍬社、八百万社、八幡社、忠敬社 
稲荷社と富野御前社 
遥拝殿と稲荷社 
天満社
地図で鎮座地を確認
| 神社名 | 御津神社 |
| 鎮座地 | 愛知県豊川市御津町広石祓田七十番地 |
| 最寄駅 | 御津地区地域路線《ハートフル号》「葵生庵前バス停」徒歩2分 |
伊勢神宮、氏神の神社、そして皆様が崇敬している神社の御神札をご自宅にお祀りされていますか?
現在ではアパートなどの賃貸住宅でも気軽に御神札を祀る事ができる神棚が登場しています。今まで賃貸住宅で神棚が置けないと御神札をお祀りできなかった方も、こうした神棚をご用意されてお祀りされてみてはいかがでしょうか?