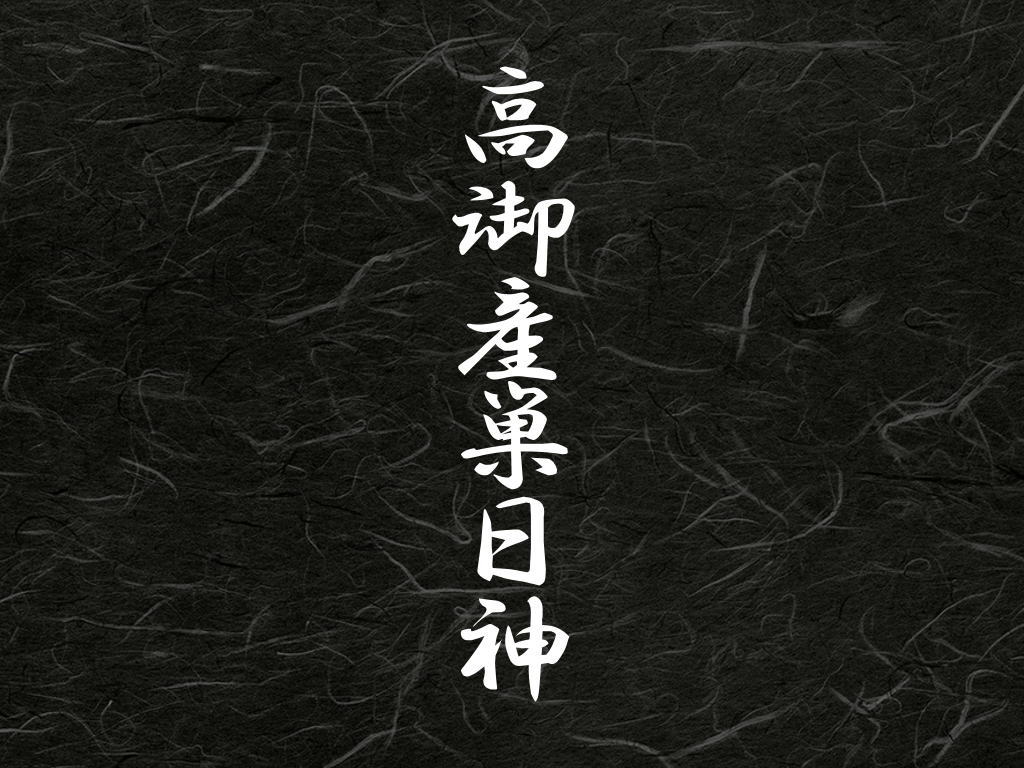高御産巣日神とは?
古事記では、天と地が分かれた時に、天之御中主神についで出現したか神であり、次に出現した神産巣日神の三柱の神の総称「造化三神」の一柱になります。
-
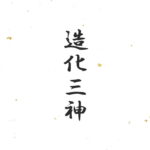
-
造化三神|天地初めて発りし時に、高天の原に成りませる神々
続きを見る
『古事記』の冒頭に「天地初めて発りし時に、高天の原に成りませる神の名は、天之御中主の神、次に、高御産巣日の神、次に、神産巣日の神。この三柱の神は、みな独神と成りまして、身を隠したまひき。」 とあるように、高御産巣日神は天と地が分かれて、天(高天原)に最初に現れた造化三神のうち、二番目に現れた神になります。
もう一方の歴史書である『日本書紀』では、本文にはその名を見る事はできず、いくつか併記されているいくつかの一書の中の一つに登場するのみとなっていて、「高皇産霊尊」と記されています。 また記紀の「国譲り・葦原中津国平定」、「天孫降臨」ではそれぞれ「高木の神」、「高木大神」という名で登場してます。さらには、 「神武東征」の際には神武天皇の危機に神剣を下し、八咫烏を遣わすなどその影響力を発揮しています。
名前の「産巣日」は生産・生成を表す言葉である事から、創造を神格化した神と言われています。
造化三神のもう一柱に、同じ「産巣日」を持つ神「神産巣日神」がいます。両神とも生成・創造を神格化した神とされ、「対偶神」であるとも言われています。
別の始点から
「高御産巣日神」の「高」は「高い所から降臨する」という意とされ、「産巣日」は「天地・万物を生成・発展・完成させる霊的な働き」という意の「むすひ」の当て字だと言われています。
この事から、高御産巣日神は、「高い所から降臨してきた生成・発展を司る神」という意になるかと思います。
こうした意から一説に元々は高天原における最高神であったが、天照大御神にその地を譲る(取って代わられて)、その後、古事記、日本書記に登場する際には「高木神」に改称しているのではないかとも。
さらに言えば、(伊勢)神宮の元々の御祭神は「高御産巣日神」であり、天智・天武天皇の頃に現在の「天照大御神」に御祭神が変更となったという伝承も残っているそうです。
神々のデータ
| 神祇 | 天津神・別天津神・造化三神 |
| 神名 | 古事記 :高御産巣日神 日本書紀:高皇産霊尊 |
| 別称 | 高木神、高木大神 |
| 親 | ー |
| 子 | 記紀:思金神 記紀:万幡豊秋津師比売命 紀:天活玉命 紀:少彦名命 紀:三穂津姫 |
高御産巣日神を祀る神社
- 比蘇天神社
鎮座地:愛知県岡崎市宮地町北浦四十二
延喜式内社:碧海郡 比蘇神社
-

-
比蘇天神社(岡崎市宮地町北浦)延喜式内社「比蘇神社」論社
続きを見る
-
まとめ
造化三神、別天津神の「高御産巣日神」と「神産巣日神」は共に成長・創造が神格化した神で対偶神であるとされていますが、古事記を読んでいくと、それぞれに特徴があったりします。
- 高御産巣日神・・高天原系の神々への助言・守護などを行う。
- 神産巣日神 ・・出雲系の神々への助言・守護などを行う。
古事記では、高天原系の神々の伝承も、出雲系の神々の伝承も取り上げているので、両神とも何度か登場し伝承が紹介されていますが、対する日本書記では出雲系の神々の伝承は基本記載されていない為、神産巣日神については、冒頭の造化三神として出現したとする一書以外にはその名を見る事がないようです。