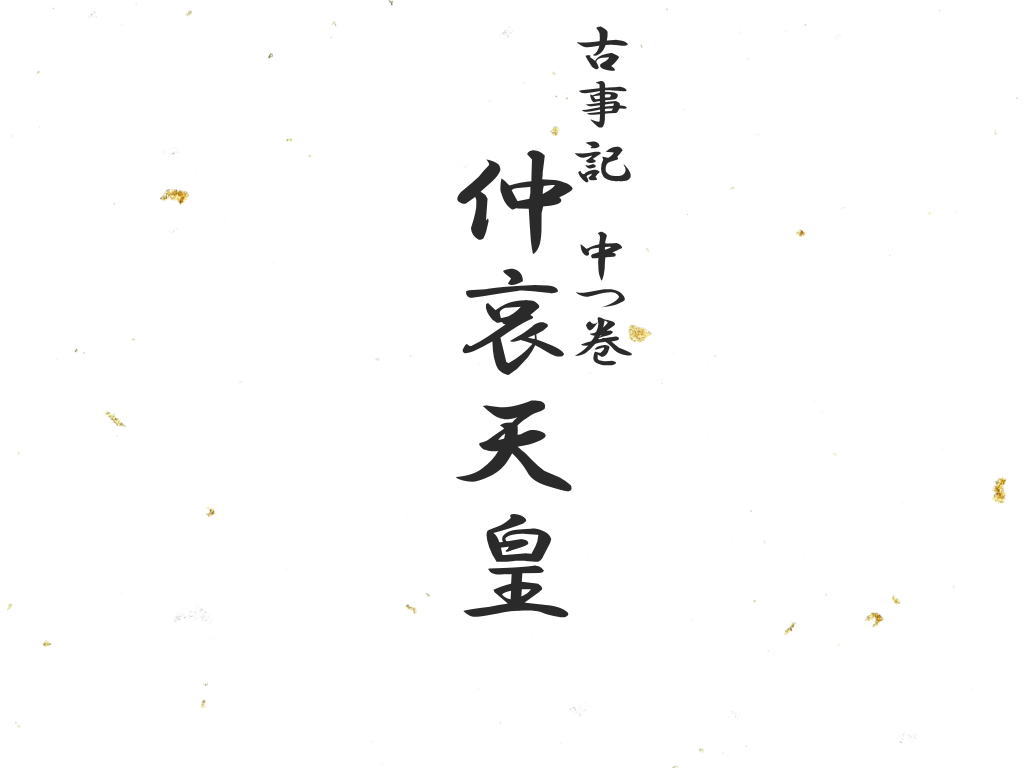皇統譜
仲哀天皇は、第十二代景行天皇の皇子で日本神話において最大の英雄とされる「倭建命(ヤマトタケル)」を父にもち、三十一歳の時に、叔父にあたる十三代成務天皇の皇太子となり、四十三歳の時に第十四代天皇と即位しています。ただ、実在性は定かではない天皇になります。
成務天皇
古事記を読む
帶中日子天皇、坐穴門之豐浦宮及筑紫訶志比宮、治天下也。此天皇、娶大江王之女・大中津比賣命、生御子、香坂王、忍熊王。二柱。又娶息長帶比賣命是大后生御子、品夜和氣命、次大鞆和氣命・亦名品陀和氣命。二柱。此太子之御名、所以負大鞆和氣命者、初所生時、如鞆宍生御腕、故著其御名。是以知、坐腹中定國也。此之御世、定淡道之屯家也。
- 帶中日子天皇は仲哀天皇の事。
- 穴門は長門国の古称であり関門海峡周辺の地域を指す。
- 息長帯比売皇命は神功皇后の事
- 大鞆和氣命、品陀和気命は応神天皇の事
- 鞆とは弓を射る時に弓弦が当たるのを防ぐ防具の事
- 淡道之屯家とは淡路島に設けられた天皇の直轄地
現代語訳
帶中日子天皇は穴門の豊浦宮、また筑紫の訶志比宮に滞在して天下を治めていた。
この天皇、
大江の王の娘、大中津比売命を娶って生まれた御子は、
香坂王、
忍熊王の二柱。
また、息長帯比売皇命を娶りて生まれた御子は、
品夜和気命、
大鞆和氣命。亦の名を品陀和気命の二柱。
後に皇太子となる御子の御名を大鞆和氣命とお付けになった理由は、生まれた時すでに、その腕には弓を射るときに付ける武具「鞆」のような盛り上がりがあった。それでその御名を付けられたのである。
この事から、まだお生まれになる前から国を治めていたのである。
仲哀天皇の御代の時、淡道之屯家が定められた。
ここでは簡素に、仲哀天皇の后とその子供たちが述べられていますが、その中で、十五代天皇となる大鞆和氣命(品陀和気)の名付けの理由がしっかりと述べられている辺り、古事記の中で応神天皇はかなり重要視されている天皇であることがここからも読み取る事ができます。
まとめ
成務天皇には嫡子が居なかった為、甥にあたる帶中日子天皇が皇太子となり、その後皇位に着いています。時の当主がしっかりと後継者を定めずに亡くなると、骨肉の跡目争いが勃発するというのはいつの時代でも共通な法則のですが、仲哀天皇の後継者争いもこの法則が発動して跡目争いが起こっています。大中津比売命・香坂王・忍熊王 対 息長帯比売皇命・品夜和気命・大鞆和氣命という構図になるのですが、まあ結果は見えていますね。この辺りは古事記でも記述がありますので、そちらで詳しく見ていく事にします。
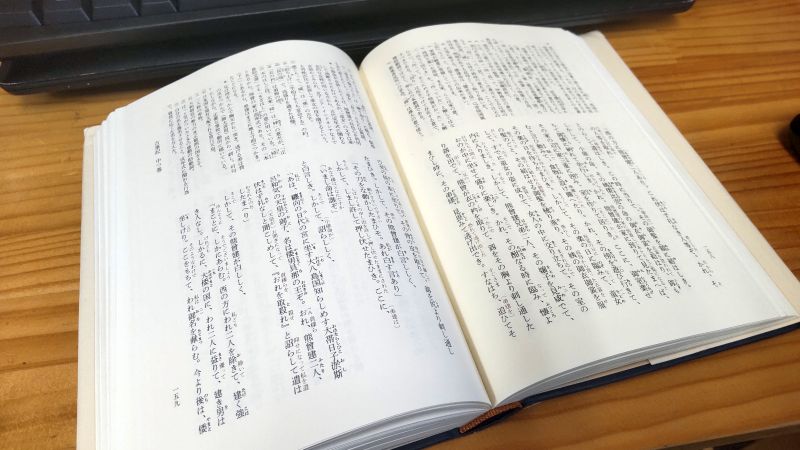
当サイトでは、古事記の現代語訳を行うにあたって、「新潮日本古典集成 古事記 西宮一民校注」を非常に参考させて頂いています。原文は載っていないのですが、歴史的仮名遣いに翻訳されている訳文とさらに色々な注釈が載っていて、古事記を読み進めるにあたって非常に参考になる一冊だと思います。
仲哀天皇|息長帯比売命と神懸り