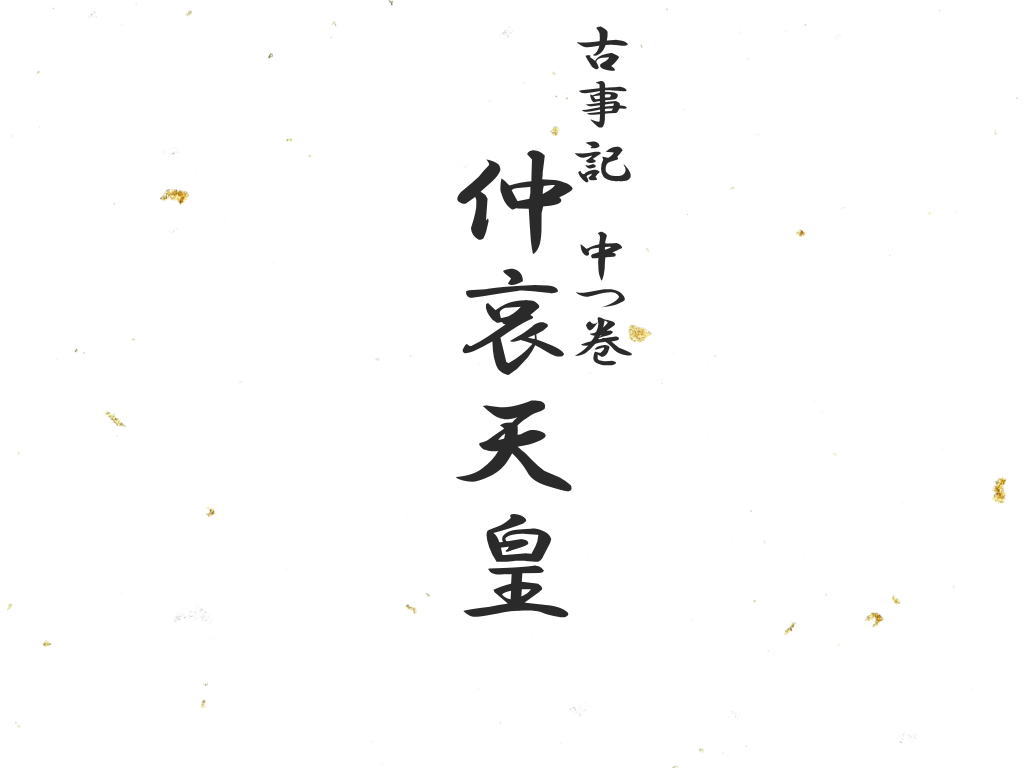神功皇后、太子に献酒
禊を行う為に、敦賀を訪れた太子は、気比神社の御祭神となる「伊奢沙和気大神命」との”ナ”の交換による服従帰属の儀礼が行われました。
敦賀から初めて大和国に入る太子を神功皇后は酒を造って迎えています。御食、酒楽と繋がる事から大嘗儀礼の原型ではないかとも言われている様です。・・・ただ、御子が立太子の儀を受けたり、即位するまでにはまだまだかなりの時間を有するわけですが・・・。
古事記を読む
於是、還上坐時、其御祖息長帶日賣命、釀待酒以獻。爾其御祖御歌曰、
許能美岐波 和賀美岐那良受 久志能加美 登許余邇伊麻須 伊波多多須 須久那美迦微能 加牟菩岐 本岐玖琉本斯 登余本岐 本岐母登本斯 麻都理許斯美岐叙 阿佐受袁勢 佐佐
如此歌而、獻大御酒。爾建內宿禰命、爲御子答歌曰、
許能美岐袁 迦美祁牟比登波 曾能都豆美 宇須邇多弖弖 宇多比都都 迦美祁禮迦母 麻比都都 迦美祁禮加母 許能美岐能 美岐能 阿夜邇宇多陀怒斯 佐佐
此者酒樂之歌也。
凡帶中津日子天皇之御年、伍拾貳歲。壬戌年六月十一日崩也。御陵在河內惠賀之長江也。皇后、御年一百歳崩、葬于狹城楯列陵也。
- 待酒とは、帰ってくる人の無事を祈りまた祝福して造り待つ酒のこと。
- 伊波多多須とは、石立たすとなり、石神の事。
現代語訳
さて、太子が都へ帰還なされた時、母である神功皇后は太子の無事を祈願して醸造した酒を太子に献上された。そしてその時皇后は歌詠みをされた。
この御酒は、私が作った酒ではありません。
常世にいらっしゃる 酒の司でる
石の様に御立の少名御神が
祝福し、祝福して踊る狂い
祝福し、祝福して踊り廻って
献上された由緒ある御酒です。
残さずお飲みなさい。 さあ、さあ
と詠い、太子に酒を献上した。そして、建内宿祢命が太子に代わって返し歌をお読みになった。
この御酒を醸造したという人は、
その鼓を臼に立てて
詠いながら醸造したのか
踊りながら醸造したのか
この御酒を飲むととても楽しい
さあさあ
これは酒楽の歌です。
おおよそ仲哀天皇は御年五十二。(壬戌の年の六月十一日に亡くなりました。)御陵は河内国の恵我の長江にあります。
神功皇后は御年百歳、壬戌年六月十一日にお亡くなりになり、狹城楯列陵に埋葬されました。
まとめ
神功皇后は大和国にて太子の帰還を待っていたという描写になっています。香坂王・忍熊王との戦いの際は行動を共にしていたと思われるので、戦いの後、穢れを払う為に太子は建内宿祢を側近として敦賀に禊に向かったのでしょう。そして禊を終えいよいよ都のある大和国に入国した際に神功皇后は旅の無事を祈願して醸造した酒を無事に到着したという事で振舞ったのでしょう。
そういえば、御子を突然「太子」と称するようになったのは、古事記の中では記されていませんが、どこかの時点で御子を皇太子としているはずです。日本書記の記述から、禊に向かったのは皇太子となってから十年ほど経ってから行われた事になっています。禊を行なおうと思わせる何らかの出来事が起こったと考えるのが妥当かなと思います。
神功皇后の摂政時代はおよそ七十年にも及びます。太子が敦賀に禊にいってからも五十年以上は太子を皇位に付けることなく、皇后が摂政として朝廷を支配しています。この事から、以前は神功皇后が日本初の女帝として皇位に着いていたのではないかと考えられていた様ですが、近年ではこの説は否定されて、あくまでも摂政として政治を取り仕切っていたとされています。
しかし、古事記では神功皇后の記述が思った以上にあっさりとしていて、この段で仲哀天皇と神功皇后の話が終わってしまい、次からは応神天皇の話へと移っていきます。(そういえば、古事記では天皇毎に段が分かれていて、神功皇后はあくまでも仲哀天皇の補足みたいな形で書かれているのも特徴の一つですね。)
応神天皇|皇統譜