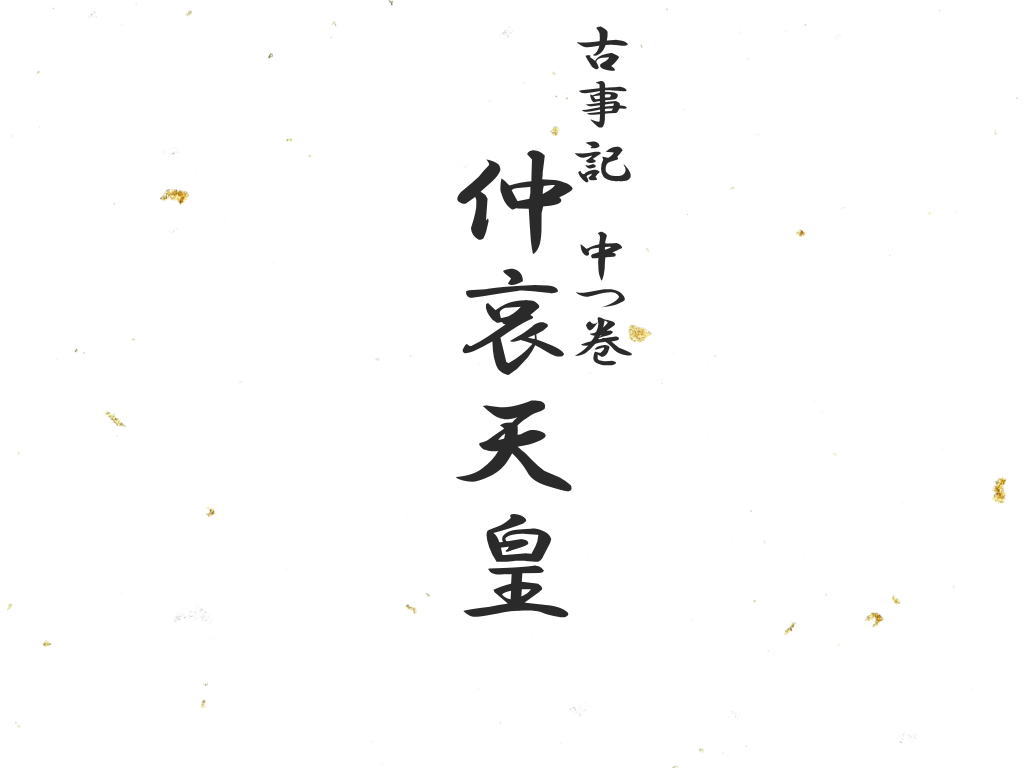息長帯比売命と神懸り
前の段で紹介している様に、仲哀天皇の皇后で、品夜和気命、大鞆和気命を生んだ息長帯比売命なんですが、一般的には和風諡名である神功皇后の名で知られているかと思います。
夫である仲哀天皇が急死し、まだ自らの胎内にいて、生まれていない天皇の間の皇子である大鞆和気命を産み育てて、皇太子になるまで育てあげ、自らは皇太子の後見となる摂政となり国政を支えるというまさに「女帝」といったイメージを神功皇后に持たれる方も多いかと思います。実はこうしたイメージもあって、明治時代の頃までは日本初の女性天皇であると言われていた様ですが、様々な研究・分析の結果、皇位にはついていなかったと結論付けられて今では歴代天皇の中にその名前を見る事はありませんが、歴代の天皇に勝るとも劣らない政治を行ってきた人物であるといえそうなのですが、残念ながらその実在性はかなり低いと言わざるを得ないようで、造られた人物像という可能性もある訳です。
そんな強烈な印象を与える神功皇后がなぜこれほどまでに求心力を得る事ができたのか。その第一歩となる出来事が今回紹介する「神懸り」になります。
古事記を読む
其大后息長帶日賣命者、當時歸神。故、天皇坐筑紫之訶志比宮、將擊熊曾國之時、天皇控御琴而、建內宿禰大臣居於沙庭、請神之命。於是、大后歸神、言教覺詔者「西方有國。金銀爲本、目之炎耀、種種珍寶、多在其國。吾今歸賜其國。」爾天皇答白「登高地、見西方者、不見國土、唯有大海。」謂爲詐神而、押退御琴不控、默坐。
爾其神大忿詔「凡茲天下者、汝非應知國。汝者向一道。」
- 當時は仲哀天皇が西国に巡幸していた時
- 訶志比宮とは仲哀天皇が筑紫国巡幸の際の行宮。日本書記では橿日宮と記す
- 向一本道とは、黄泉の国へは一本道しかないという意
現代語訳
仲哀天皇の皇后の息長帯比売命は、西国に巡幸中に神懸りされました。
それは、仲哀天皇が熊襲を征伐する為、筑紫の訶志比の宮に滞在していた時、天皇は琴を弾かれ大臣である建内宿祢が斎場にて神の神託を求めた。この時、神功皇后は神懸りされ、神託で教える様に仰せられた。
「西方に国がある。金・銀をはじめ、眩いばかりの様々な珍しい宝が多くその国にはある。我が今その国を服従させてよう。」
しかし、天皇は
「高い場所に登って西方を見てみたが、まったく国は見えず、見えるのは海ばかりだ。」
と答え、偽りをいう神であると思い、御琴を脇に押しやりひくのを止め、黙っておられた。
神は大変お怒りになり、
「この天下は、そなたが治める国ではない。今すぐ黄泉の国に行くがいい。」
コラム
この神懸りの場面は「日本書紀」にも描かれています。
日本書紀では、熊野征伐の為に仲哀天皇が穴門の豊浦宮から筑紫国に進軍した時、滞在した橿日宮にて軍議を開いた。この時、神功皇后が神懸りとなり、「不毛な土地する熊襲の国を攻めるのだ。それより海の向こうにある豊かな国である新羅を攻め落とせば、熊襲の国も手に入れる事ができる。」と神託したが、仲哀天皇は、高い山から望んでも国は見えず、海ばかりであるとして、神託を信じず、そのまま熊襲攻めを強行するといった内容になります。
仲哀天皇がいかに熊襲攻めに向かったのかというのは日本書記の方がしっかりと記述されています。ぜひとも、解説記事を参照してみてさい。
-

-
巻第八 仲哀天皇<足仲彦天皇>|熊襲征伐に向う
熊襲征伐 前回では、皇位に着いた仲哀天皇は、神功皇后と共に越国敦賀に「笥飯宮」を建てたという所まで見てきました。敦賀に建てた笥飯宮の跡地は現在では「気比神社」の境内地になっていると伝承されており、こ ...
続きを見る
まとめ
科学が進んだ現代と違い、古代は神の神託というのは政に非常に大きな要素であったのはご存知の通りです。古事記、日本書紀に書かれている様に、霊媒者に神霊が乗り移る神懸りであったり、亀の甲羅などをつかった占う「亀卜」であったり様々な方法で神託を得ようとしていました。そんな古代の政の一端を知る事ができる場面になるかと思います。
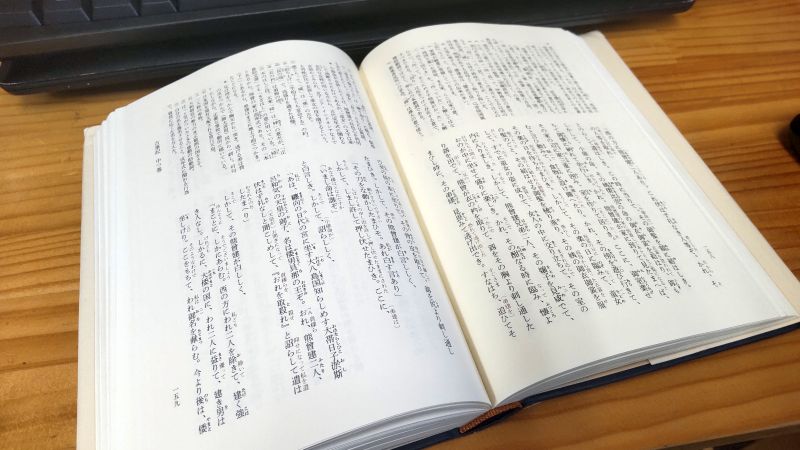
当サイトでは、古事記の現代語訳を行うにあたって、「新潮日本古典集成 古事記 西宮一民校注」を非常に参考させて頂いています。原文は載っていないのですが、歴史的仮名遣いに翻訳されている訳文とさらに色々な注釈が載っていて、古事記を読み進めるにあたって非常に参考になる一冊だと思います。