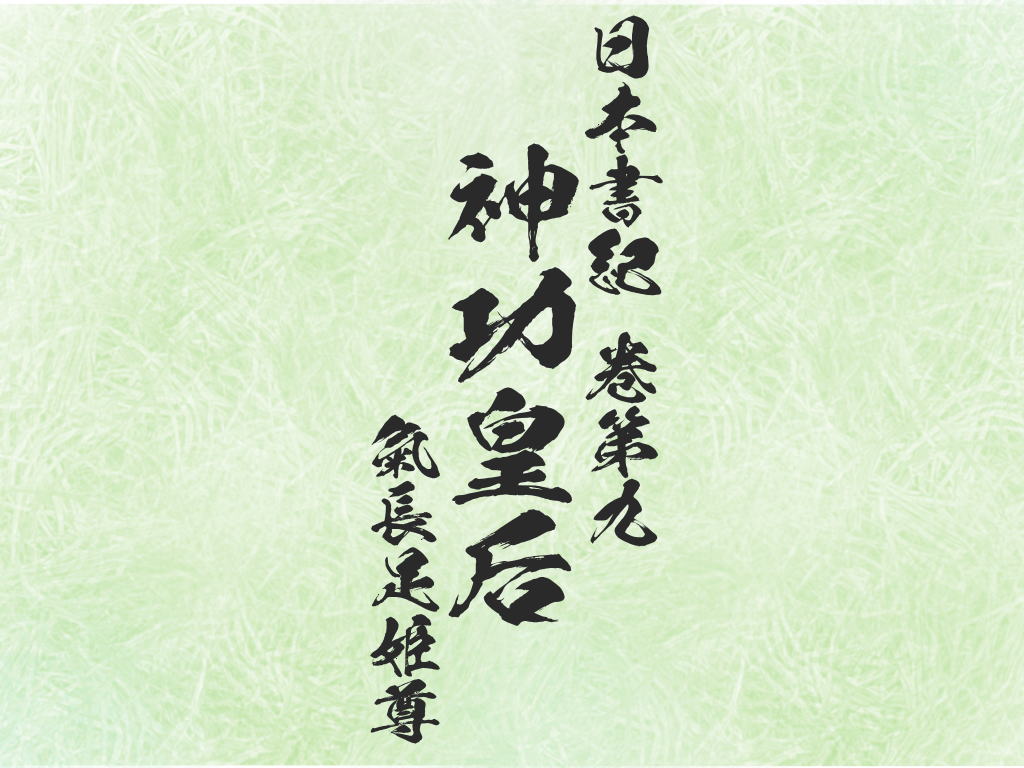新羅征伐軍を興す
神功皇后は橿日宮とその西側に広がる橿日浦にて「大海の向うにあるという宝の国を欲する」という詔を発して、それまではあくまでも「神懸りと神託」という仲哀天皇の意向に沿って皇后が動いていたどちらかと言えば私的といえる行動から、詔を発することで「国」としての行動フェーズに移行した事を示しているといえます。
詔を発したからすぐに遠征軍が編成できるわけではなく、何ヶ月もかけて軍を編成していく事になります。ヤマト朝廷としての国策による新羅征伐であるとはいえ、ヤマト朝廷の勢力圏全土から徴兵されたという訳ではなく、その主な徴兵先は九州地方にかなりの比重が置かれていた様です。
神功皇后が北九州一体の平定の為軍勢を率いて各豪族を打ち破っていたのも、兵士、軍備、食料の供出を迫ったヤマト朝廷に対して反抗した勢力に対する懲罰の意味もあったのではないかと思っています。
九州を平定した上での行われている遠征軍の編成ですが、どうやら一筋縄ではいかなかった様です。
日本書記を読む
秋九月庚午朔己卯、令諸國、集船舶練兵甲。時軍卒難集。皇后曰、必神心焉、則立大三輪社、以奉刀矛矣。軍衆自聚。於是、使吾瓮海人烏摩呂、出於西海、令察有國耶。還曰、國不見也。又遣磯鹿海人名草而令視。數日還之曰、西北有山。帶雲横絚。蓋有國乎。爰卜吉日、而臨發有日。時皇后親執斧鉞、令三軍曰、金鼓無節、旌旗錯亂、則士卒不整。貪財多欲、懷私內顧、必爲敵所虜。其敵少而勿輕。敵强而無屈。則姧暴勿聽。自服勿殺。遂戰勝者必有賞。背走者自有罪。既而神有誨曰、和魂服王身而守壽命。荒魂爲先鋒而導師船。【和魂、此云珥岐瀰多摩。荒魂、此云阿邏瀰多摩。】卽得神教、而拜禮之。因以依網吾彦男垂見爲祭神主。于時也、適當皇后之開胎。皇后則取石插腰、而祈之曰、事竟還日、産於茲土。其石今在于伊都縣道邊。既而則撝荒魂、爲軍先鋒、請和魂、爲王船鎭。
- 秋九月庚午朔己卯は仲哀天皇九年九月十日
- 軍卒とは兵士の意
- 大三輪社は朝倉郡筑前町に鎮座する大己貴神社に比定されています。
- 伊都縣は福岡県糸島市の辺りを指す。
現代語訳
仲哀天皇九年九月十日、諸国に対して、渡海用の船の徴集、兵士の鍛錬が命じられた。しかし、兵士の徴兵がうまくいかなかった。この事態に神功皇后は、
「これも神の御意思に間違いない。」
として、すぐに大三輪社を建立、刀と矛を献納された。その後、兵士は自然に集まったという。
そして、吾瓮の海人である烏摩呂を遣わして西の海の先に国があるかを偵察させた。烏摩呂は偵察から戻ってきて「国は見えませんでした。」と報告した。
もう一人、磯鹿の海人である名を草と申す者にも西の海の先に国があるかを偵察させた。草は数日をかけて偵察を行い、「西北に山が見え、その山に厚い雲がかかっていて、国があると思われます。」と報告した。
吉日を占い、出陣する日を決め、この時神功皇后は自ら斧、鉞を手に取り、全軍の兵士に向かい
「陣太鼓や軍旗が乱れる様であれば、兵列は整わないだろう。財をり、物欲、私欲、自己のことばかりに心を奪われていれば、必ず敵に捕らえられてしまうだろう。敵が少なくても侮るな。敵が多くても怖気づくな。婦女暴行は決して許されない。降伏してきた者を殺すな。戦に勝てば恩賞を与えよう!。背走する者には罪をあたえよう!」
と述べられました。
そして、神勅があり、
「和魂は皇后に従いその命を守ろう。荒魂は軍の先鋒となり軍船を導こう。」【和魂はニギミタマと読み、荒魂はアラミタマと読む】
この神勅を聞いた皇后はすぐさま拝礼し、依網吾彦男垂見を祭主に任じました。また、遠征に出陣する月は、皇后の出産月にあたっていましたが、皇后は石を取り腰に挟み、
「遠征を終え、この国に戻ってきた時に出産させてください。」
と祈願しています。この時の石は、伊都縣の道のほとりにあるといいます。
こうして、荒魂を招き寄せて軍の先鋒とし、和魂を請じて船の守りとされた。
まとめ
橿日宮にて新羅国侵攻の為の軍勢を整えていましたが、予想以上に軍勢の集まりが悪かった事から、「これも神の御教えなのだろう。」と神を奉斎する為に建立された神社が「大三輪社」であるとし、現在では「大己貴神社」が大三輪社であると比定されています。
大己貴神社
この大三輪社であると比定されている大己貴神社の境内地がある場所は、神功皇后が軍を率いて制圧した羽白熊鷲が治めていたという荷持田村とは目と鼻の先の場所になり、対羽白熊鷲の戦いの際の行宮として造られた松峽宮からも非常に近い場所になります。
軍勢の徴兵がうまく進まないのが神の教えであるとするならば、橿日宮近くに神社を建立すればいいはずな訳です。それを何故少し前まで敵対していた勢力の近くに神社を建立したのか。
いくら臣従したとはいえ、新羅遠征の為の兵士や軍備の供出には非常に消極的だった荷持田村に対し、圧力をかける為に建立された神社であったのではないかと考えています。そして、神社を建立、奉斎する事により、荷持田村からの兵士・軍備の供出が予定通り行われたという事なのではないでしょうか。
大己貴神社公式サイト
神武皇后の腰石
腰に石を巻き付ける事により出産日を遅らせるという記述は「古事記」でも記されています。古事記では、「新羅征伐の途中で陣痛に襲われ、石を巻き付けて、帰国するまで出産を遅らせた。」といった内容でした。陣痛が始まった時期は異なりますが、新羅征伐から帰国するまで出産時期を延ばすとした内容はほぼ同一の様です。
この時、神功皇后が挟んでいたという石を鎮懐石と呼び、皇子を出産後にその石を納めた場所が古事記、日本書紀共に伊都(伊斗)縣にあると記しています。現在この場所には、鎮懐石八幡宮が鎮座して、安産の神として崇敬を集めているそうです。
巻第九 神功皇后|新羅征伐