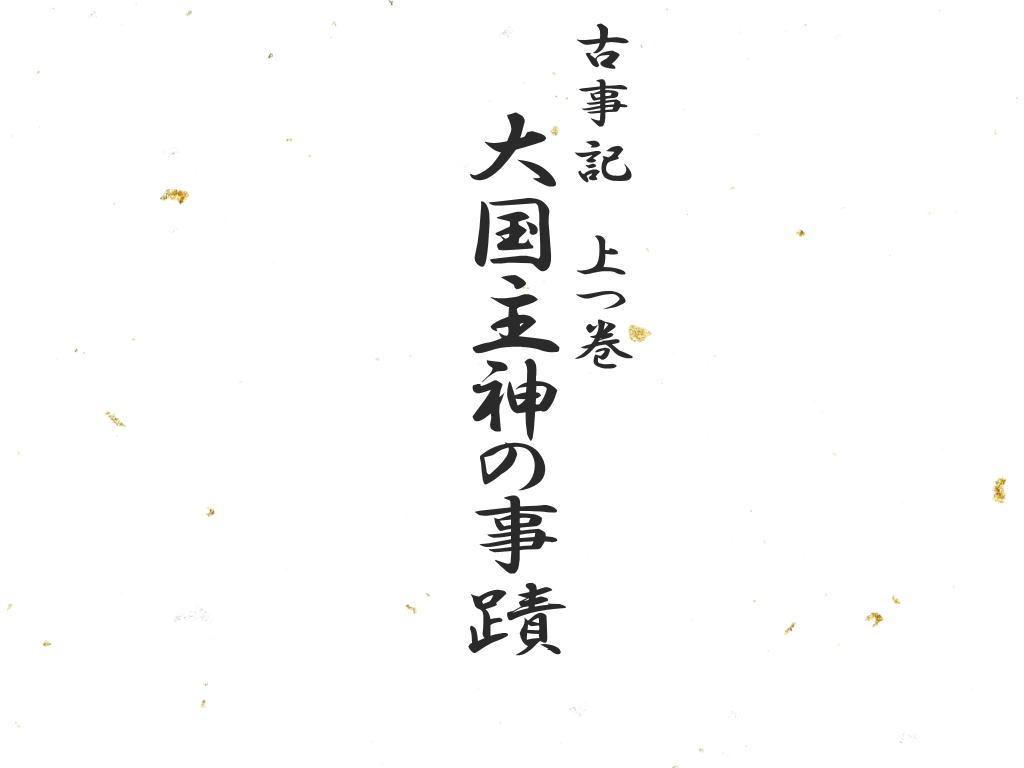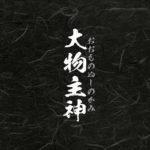御諸山の神を祀る
大国主神と共に国造りを行ってきた少名毘古那であったが、ある時、少名毘古那は大国主神の元を離れ、海原の彼方の常世国に渡っていってしまいます。
少名毘古那神の協力を得て国作りをすすめる
古事記をよむ
於是大國主神愁而。告吾獨何能得作此國。孰神與吾能相作此國耶。是時。有光海。依來之神。其神言。能治我前者。吾能共與相作成。若不然者。國難成。爾大國主神曰。然者治奉之状奈何。答言。吾者。伊都岐奉于倭之青垣東山上。此者坐御諸山上神也。
- 依來之神:古代の人々は海の彼方からやってくる人を幸福の神として崇めたという。
- 倭之青垣東山上:大和国を囲んでる山々の東側にある三輪山を指す。
現代語訳
ここに、大国主神は困って仰せられたのは、
「私ひとりで、どうやって国造りを行えばいいのか。どういった神ならば私と協力して国造りを行う事ができるだろうか。」
この時、海を光らせて近づいてくる神がいた。その神はいうには、
「私の御魂を祀ってくれるのであれば私が協力し、この国造りを完了させよう。しかし、そうしなければ、国作りは終わらないだろう。」
これを聞いた大国主神は、
「でしたら、御魂のどのようにお祀りすればよろしいでしょうか。」
と尋ねると、
「私を倭の青垣の東の山の上に身を清めて祀るがいい。」
と答えられた。この神こそ、御諸山の上に鎮座する神である。
大国主神と共に国造りを行ってきた少名毘古那神が常世国に旅立ってしまい、一人残された大国主神が途方に暮れている場面になります。そんな中、海の彼方から海を光らせてやってくる神が登場します。
この神の名は「大物主神」であるとされていますが、この段では大物主神の名は登場せず「坐御諸山上神」という神名で登場しています。古事記の神武天皇の段の中に「美和の大物主神」として登場していて、「三輪=美和」となり、御諸山は三輪山を指している事から御諸山に鎮座する神は大物主神であると考えられている様です。
この大物主神について、古事記と日本書記ではその立場に大きな違いがあります。
- 古事記では、大国主神と大物主神は非常に緊密な神であるが別神としている。
- 日本書紀では、大国主神の幸魂・奇魂が大物主神であるとして同一神としている。
同一神か別神なのかは非常に難しい所なのですが、出雲系である大国主神、またはそれに非常に近しいである大物主神が倭(大和国)の都近くに祀られている事に古代日本のヤマト朝廷と出雲国の関係が見えてきそうな気がします。
今回登場した神々
| 大国主神 | おおくにぬしのかみ | 国津神 |
| 坐御諸山上神 | みもろのやまのうえにますかみ | 国津神 |
まとめ
大国主神は大物主神の助力を得て、国作りを遂行することになります。そして、大国主神が作り上げた国は高天原にいた天照大御神の目に留まり、大国主神のいる葦原中つ国を御子である正勝吾勝々速日天之忍穂耳命に統治させようと大国主神に対し国譲りを迫っていくことに繋がっていきます。
この国譲りについては、古代日本におけるヤマト朝廷と出雲国との戦いを描き、最終的に出雲国が負け、ヤマト朝廷に吸収されていく様を表していると言われています。
大年神の子孫