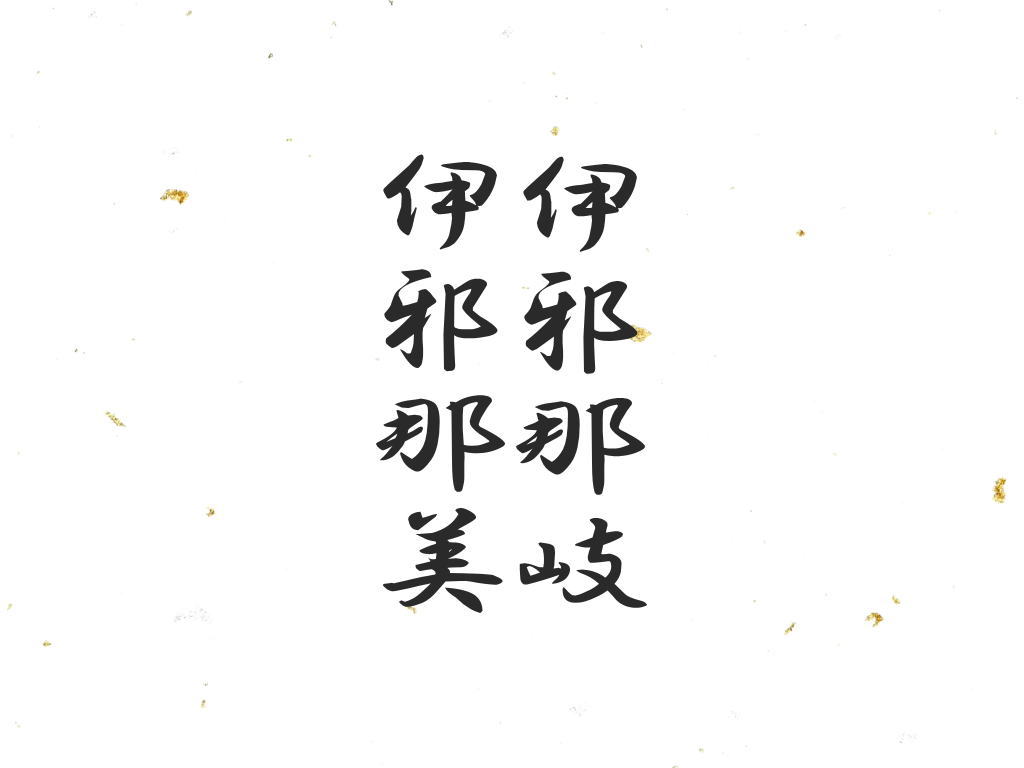伊邪那岐命、禊をする
古事記をよむ
是以伊邪那伎大神詔。吾者到於伊那志許米〈上〉志許米岐〈此九字以音。〉穢國而在祁理。〈此二字以音。〉故吾者爲御身之禊而。到坐竺紫日向之橘小門之阿波岐〈此三字以音。〉原而。禊祓也。故於投棄御杖所成神名。衝立船戶神。次於投棄御帶所成神名。道之長乳齒神。次於投棄御裳所成神名。時置師神。次於投棄御衣所成神名。和豆良比能宇斯能神。〈此神名以音。〉次於投棄御褌所成神名。道俣神。次於投棄御冠所成神名。飽咋之宇斯能神。〈自宇以下三字以音。〉次於投棄左御手之手纒所成神名。奧疎神。〈訓奧云於伎。下效此。訓疎云奢加留。下效此。〉次奧津那藝佐毘古神。〈自那以下五字以音。下效此。〉次奧津甲斐辨羅神。〈自甲以下四字以音。下效此。〉次於投棄右御手之手纒所成神名。邊疎神。次邊津那藝佐毘古神。次邊津甲斐辨羅神。 右件自船戶神以下。邊津甲斐辨羅神以前。十二神者。因脫著身之物所生神也。於是詔之上瀨者瀨速。下瀨者瀨弱而。初於中瀨随迦豆伎而。滌時。所成坐神名八十禍津日神。〈訓禍云摩賀。下效此。〉次大禍津日神。此二神者。所到其穢繁國之時。因汚垢而所成神之者也。次爲直其禍而所成神名神直毘神。〈毘字以音。下效此。〉次大直毘神。次伊豆能賣神〈并三神也。伊以下四字以音。〉次於水底滌時。所成神名。底津綿〈上〉津見神。次底筒之男命。於中滌時。所成神名。中津綿〈上〉津見神。次中筒之男命。於水上滌時。所成神名。上津綿〈上〉津見神。〈訓上云宇閇。〉次上筒之男命。此三柱綿津見神者。阿曇連等之祖神以伊都久神也。〈伊以下三字以音。下效此。〉故阿曇連等者。其綿津見神之子。宇都志日金拆命之子孫也。〈宇都志三字以音。〉其底筒之男命中筒之男命上筒之男命三柱神者。墨江之三前大神也。
- 伊邪那伎大神とは、命もちができなくなった為、命から神になった。
- 竺紫日向之橘小門之阿波岐原は、宮崎県宮崎市の大淀川北岸の橘の江田神社周辺と比定されている。
現代語訳
(黄泉の国から脱出した)伊邪那岐大神は
「私は見るのもいやな醜い、穢い国に行ってきてしまった。だから、禊を行わなければ。」
と仰せになり、筑紫の日向の橘の小戸の阿波岐原に到りて、禊祓を行われた。
それで、投げ棄てた御杖に出現した神の名は、衝立船戸神。
次に投げ棄てた御帯に出現した神の名は、道之長乳歯神。
次に投げ棄てた御嚢に出現した神の名は、時量師神。
次に投げ棄てた御衣に出現した神の名は、和豆良比能宇斯能神。
次に投げ棄てた御褌に出現した神の名は、道俣神。
次に投げ棄てた御冠に出現した神の名は、飽咋之宇斯能神。
次に投げ棄てた左の御手の手纏に出現した神の名は、奥疎神。
次に奥津那芸佐毗古神。
次に、奥津甲斐弁羅神。
次に投げ棄つる右の御手の手纏に出現した神の名は、辺疎神。
次に辺津那芸佐毗古神。
次に辺津甲斐弁羅神。
右の船戸神から辺津甲斐弁羅神までの十二柱の神は、(伊耶那伎大神が)身に著けていた物を脱いだことによって生んだ神である。
そこで伊耶那岐命は、「上の瀬は流れが激しい。下の瀬は流れが弱い」と仰せられ、
初めて中ほどの瀬に飛び込んで身をすすいだ時に出現した神の名は、八十禍津日神。
次に、大禍津日神。
この二柱の神は、あのけがれのはなはだしい国に行った時に、けがれによって出現した神である。
次に、このまがことを直そうとして出現した神の名は、神直毘神。
次に、大直毘神。
次に、伊豆能売[合わせて三柱の神である]。
次に、水の底で身をすすいだ時に出現した神の名は、底津綿津見神。
次に、底箇之男命。
水の中ほどで身をすすいだ時に出現した神の名は、中津綿津見神。
次に、中箇之男命。
水の表面で身をすすいだ時に出現した神の名は、上津綿津見神。
次に、上箇之男命。
この三柱の綿津見神は、阿曇連らが祖神として祭り仕える神である。
その阿曇連らは、この綿津見神の子、宇都志日金析命の子孫である。
また、この底箇之男命・中箇之男命・上箇之男命三柱の神は、墨江の三前の大神である。
まとめ
黄泉の国から逃げ帰ってきた伊邪那岐は、黄泉の国で自らの体にまとわりついた「穢れ」を洗い流す為に、現在の宮崎県宮崎市に鎮座する江田神社のちかくにある「みそぎの池」と呼ばれる場所の周辺で「禊」を行ったとされています。
参照:みやざきの神話・伝説・伝承「みそぎ池(正式名「御池」)
禊に先立ち、伊邪那岐の抜いた衣服などから十二柱の神々が化生なされます。
- 御杖から「衝立船戸神」
- 御帯から「道之長乳歯神」
- 御嚢から「時量師神」
- 御衣から「和豆良比能宇斯能神」
- 御褌から「道俣神」
- 御冠から「飽咋之宇斯能神」
- 左手の手纏から「奥疎神」、「奥津那芸佐毗古神」、「奥津甲斐弁羅神」
- 右手の手纏から「辺疎神」、「辺津那芸佐毗古神」、「辺津甲斐弁羅神」
この順番は、伊邪那岐が禊を行うにあたって身に着けていた衣装を脱ぎ去った時の順番となっています。
持っていた杖をおき、帯をほどき、腰あたりにぶら下げていた袋をはずし、衣を脱ぎ、褌を脱ぎ、冠を外し、鏝を左、右の順番で外していったことがここで分ります。
衣服を脱ぎさった伊邪那岐は流れのはやい上の瀬、流れがゆるやかな下の瀬ではなく、その中間でほどほどの場所である「中の瀬」に入り、穢れを洗い流す様に水をすすぐと、洗い流した場所からもつぎつぎと神が化成なされていきます。
- 中の瀬に飛び込んだ時に身に着いた穢れから「八十禍津日神」、「大禍津日神」
- 禍を直そうとしたときに「神直毘神」、「大直毘神」、「伊豆能売」
- 水の底で身をすすいだときに「底津綿津見神」、「底箇之男命」
- 中ほどで身をすすいだときに「中津綿津見神」、「中箇之男命」
- 水の上で身をすすいだときに「上津綿津見神」、「上箇之男命」
禊はまだ続いていき、右目、左目、口をすすぐときに「三貴子」と呼ばれる神々が化生なされるのですが、この辺りは次回紹介していきます。この三貴子を合わせて十柱の神々が禊からお生まれになったと古事記にかかれています。
伊邪那岐・伊邪那美|三貴子の誕生と分治