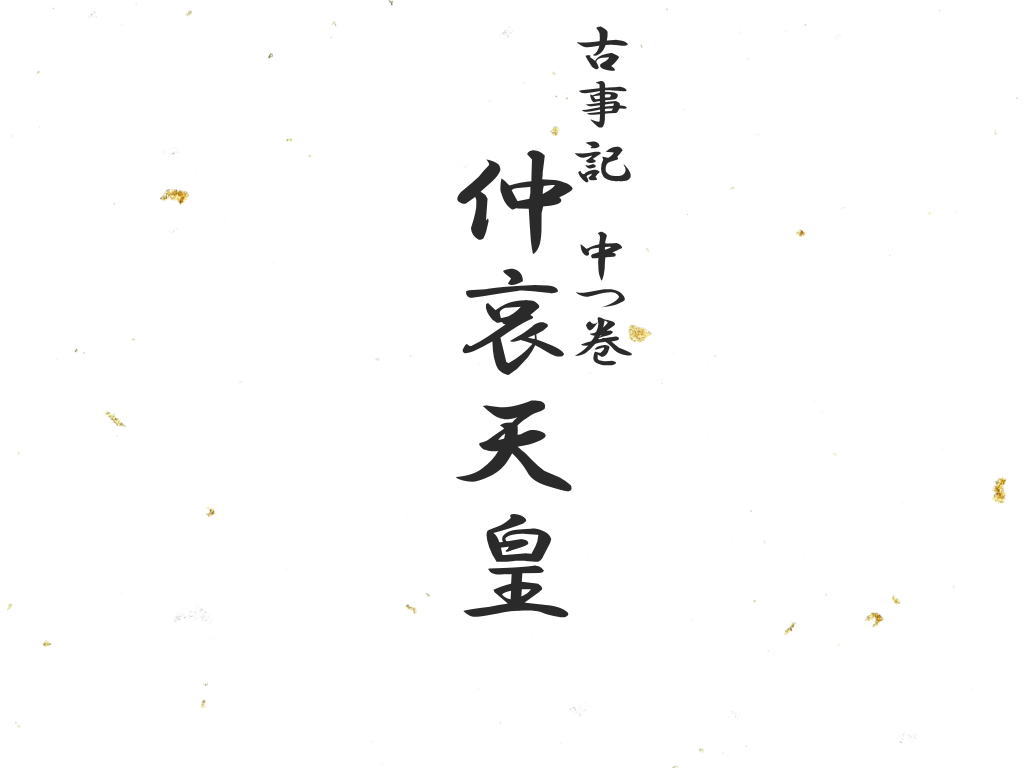太子と角鹿の気比の大神
太子(神功皇后の御子)が筑紫国から大和国に戻る途中、異母兄である香坂王・忍熊王が皇位継承を狙い、軍勢を布陣させており、ここに仲哀天皇の跡目争いが勃発します。計略を用いて優位に戦いを進める太子方に対し、劣勢となった忍熊王は最後には琵琶湖に船をこぎだし、将軍に任命していた伊佐比宿祢と共に琵琶湖に入水し、ここに跡目争いは決着します。
跡目争いに勝利した太子は、「禊」を行う為に若狭国に向かう事になるのですが・・・。
コラム
なぜ、太子は「禊」を行ったのでしょうか?
ひとつは、異母兄である香坂王・忍熊王による反逆による穢れを払う為とされています。特に、受けた争いとはいえ、異母兄を入水するまで追い詰めてしまったという兄殺しという罪・穢れを払うという意味合いも大きいのかなとおもいますが、もう一つの説が、敵を欺くために太子が死亡したという言い触らしたという「死」という穢れを利用した為、この穢れを払う為に禊を行ったというものです。どちらにしても「死」が関わっている為、この穢れを払う為の禊であると言えると思います。
古事記を読む
故、建內宿禰命、率其太子、爲將禊而、經歷淡海及若狹國之時、於高志前之角鹿、造假宮而坐。爾坐其地伊奢沙和氣大神之命、見於夜夢云「以吾名、欲易御子之御名。」爾言禱白之「恐、隨命易奉。」亦其神詔「明日之旦、應幸於濱。獻易名之幣。」故其旦幸行于濱之時、毀鼻入鹿魚、既依一浦。於是御子、令白于神云「於我給御食之魚。」故亦稱其御名、號御食津大神、故於今謂氣比大神也。亦其入鹿魚之鼻血臰、故號其浦謂血浦、今謂都奴賀也。
- 淡海は琵琶湖の事であり近江国をさす
- 高志前の高志は越国の旧名であり、高志が三分割されその内の一つが高志前と呼ばれ後に越前となった
- 角鹿は敦賀をさす
- 伊奢沙和氣大神之命は敦賀気比神社の祭神
- 言禱とは神を祝福して申し上げるという意から祝詞を奏上するという意になる
現代語訳
そこで、建内宿祢命は太子を連れて、禊を行う為に、琵琶湖(近江国)、若狭国を経由して越前国の角鹿に仮宮を造営してそこに滞在した。
この時、角鹿においでになる伊奢沙和気大神命が宿祢の夢の中に現れ、
「我が名と差し上げて、御子の御名に変えたいと思う。」
と伝え、宿祢は祝詞を奏上し、
「とても恐れ多いことです。御言葉の通りに御子の御名をお代え申し上げます。」
また、神は
「明日の朝。浜を訪れるがいい。そこに名を代えて下さったお礼の幣を差し上げよう。」
と仰せになられた。
そこで、次の日の朝、太子が浜を訪れてみると、鼻が傷ついた海豚が浜に打ち上げられていた。
これをみた太子は使いを通して神に奏上した。
「私に御食の魚が与えられた。」
そこで、その大神の御名を改めて御食つ大神と号した。今の気比神社の祭神である。
また、海豚の鼻からしたたりおちていた血はとても臭く、その打ち上げられた浦を血浦と呼ぶようになり、今では都奴賀という。
この部分を読んでいると、書いている事がよくわからなくなるんじゃないかと思います。建内宿祢の夢に出てきた伊奢沙和気大神命は「私と太子と名を交換しよう。」と言っている訳ですが、古事記では太子は「宇美」と名付けられたと記されている事から、伊奢沙和気大神命は「宇美つ大神」になって、太子は「イザサワケノミコト」となるはずですが、全く名を交換している雰囲気は微塵も感じません。
ここに書かれているのは、太子が神から海豚を与えられ、太子から神には「与えられた海豚を御食と呼んだ事から「御食」の名が与えられています。魚と名前の交換が行われたという事ですね。これをどう解釈したらいいんだろう・・・と悩んでいたんですが、魚(ナ)と名(ナ)を交換したという説がようです。これを説を知った時、一気にこの部分が違和感なく読み取れることが出来たので、ここに紹介しておきます。
まとめ
神功皇后は近江、若狭、丹後、丹波を支配していた一族の出身であり、古事記では書かれていませんが日本書紀では、仲哀天皇は神功皇后を連れて、都から巡幸の一番初めに敦賀に笥飯宮を造営したとあります。この笥飯宮の跡地に気比神社が造営されたとも言われていて、仲哀天皇、神功皇后、応神天皇にとって非常にゆかりのある場所であると言えると思います。