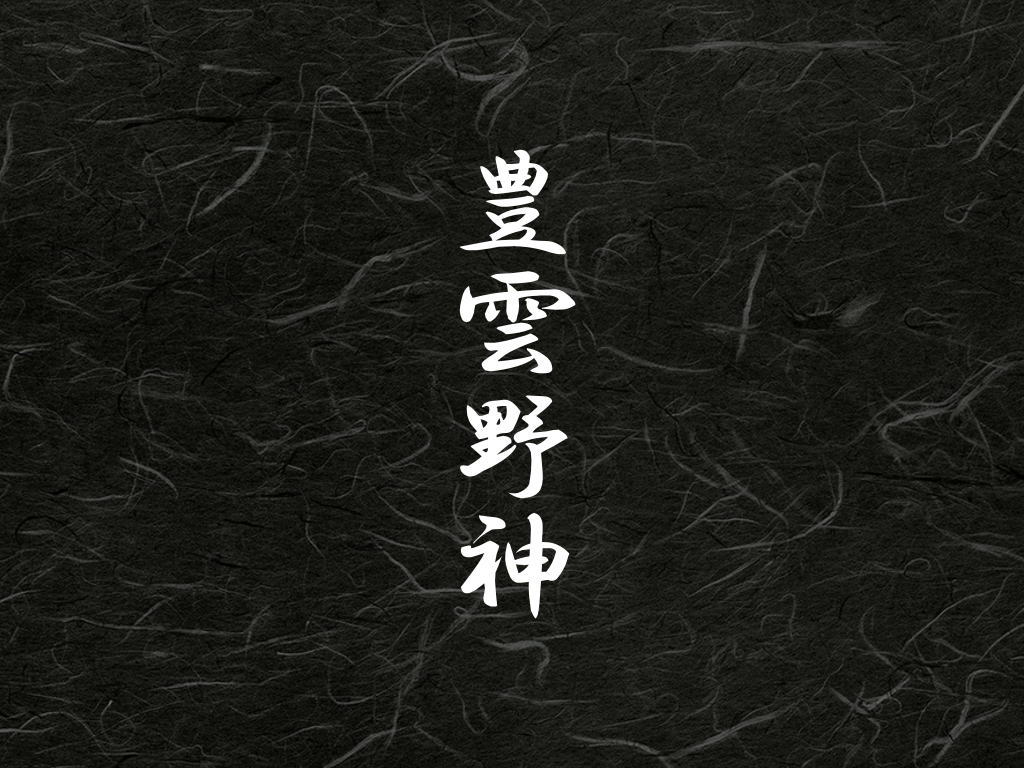豊雲野神とは?
記紀での出現状況
- 古事記に登場
神世七代の第二代で最後の独神として出現。 - 日本書紀に登場
本伝では天地開闢の中、三番目に男神として出現。 - 神名について
・古事記:豊雲野神
・日本書記:豊斟渟尊、豊国主尊、豊組野尊、豊香節野尊、浮経野豊買尊、豊国野尊、豊齧野尊、葉木国野尊、見野尊
古事記・日本書記共に出現する神になります。国之常立神(国常立尊)により地が定まった後に、「豊かな実りと雨をもたらす雲のある野原」から神格化したとされる「豊雲野神」が出現した事により、人々が住む台地は非常に豊かな台地であり続ける事を祈願したんだろうと思います。豊かな実りを支える台地は人々の生活の根本であることから、非常に重要な位置付けの神であるといえます。
古事記では、「次に、成りませる神の名は、国之常立の神。次に、豊雲野の神。この二柱の神も、独神と成りまして、身を隠したまひき。」とある様に、「国之常立神と同様に独神として出現し、すぐに身を見えなくした。」とあります。ただ、非常に重要な神だと思うのですが、豊雲野神の登場はここだけで、以後は一切登場してこない神になります。
-
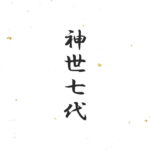
-
神世七代|地に生まれし七代の神々
続きを見る
日本書紀では、「于時天地之中生一物 狀如葦牙 便化爲神 號國常立尊 次國狹槌尊 次豐斟渟尊」と書かれていて、これを現代文に訳すと、「一つの物が天地の間に現れ、その形が葦の芽のようであったのが、やがて神とおなりになったのが国常立尊である。次に国狭槌尊、次に豊斟渟尊と全部で三柱の神が出現しました。」となります。」となり、国常立尊、国狭槌尊についで三番目に出現した神として書かれています。ただ、日本書紀も古事記同様に豊斟渟尊はここのみの登場となっています。
-

-
巻第一神代 上|天地開闢
続きを見る
神々のデータ
| 神祇 | 天津神・神世七代 |
| 神名 | 古事記 :豊雲野神 日本書紀:豊斟渟尊 |
| 神明の意味 | 豊かな実りを約束する地味の貯えた、そして慈雨をもたらす雲が覆う原野 |
| 別称 | 豊国主尊、豊組野尊、豊香節野尊、浮経野豊買尊 豊国野尊、豊齧野尊、葉木国野尊、見野尊 |
| 親 | ー |
| 子 | ー |
豊雲野神を祀る神社
- 野神社
愛知県豊田市野口町水別日面226
延喜式内社:三河国加茂郡 野神社
-

-
野神社(愛知県豊田市野口町)延喜式内社
続きを見る
-
まとめ
日本書紀は本伝とは別に、「一書曰」で始まる別伝が併記されているのが特徴なんですが、豊雲野神が重要な神である事がここでもわかるのですが、神名を変えながらも第一の別伝で登場しています。この第一別伝では、豊雲野神の別称が複数あげられていて、名前を変えながら全国各地で祀られていた神である事が見えてきます。
| 伝承 | 一代 | 二代 | 三代 | 四代 | 五代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 古事記 (神代七代) | 国之常立神 | 豊雲野神 | 宇比地邇神 須比智邇神 | 角杙神 活杙神 | 意富斗能地神 大斗乃弁神 |
| 日本書紀本文 | 国常立尊 | 国狭槌尊 | 豊斟渟尊 | ||
| 日本書紀別一 | 国常立尊 | 国狭槌尊 | 豊国主尊 |