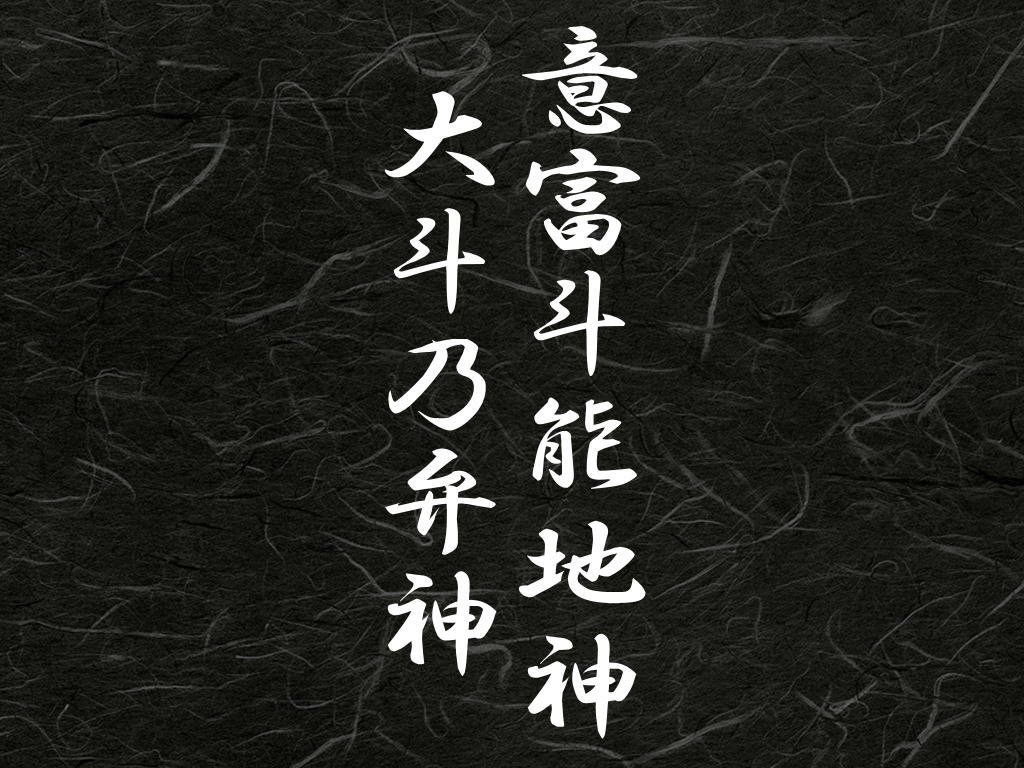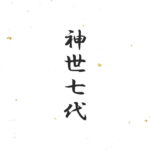意富斗能地神・大斗乃弁神とは?
記紀での出現状況
- 古事記に登場
神世七代の第五代の陰陽神として出現。
・神名:陰神:意富斗能地神 陰神:大斗乃弁神
【神代七代】
国之常立神 ー 豊雲野神 ー 宇比地邇神・須比智邇神 ー 角杙神・活杙神 ー 意富斗能地神・大斗乃弁神 ー 於母陀流神・阿夜訶志古泥神 ー伊邪那岐神・伊邪那美神
- 日本書記に登場
天地開闢にて五番目に始めての陰陽神として出現。
・神名:陽神:大戸之道尊 陰神:大苫辺尊
【神代七代】
国常立尊 ー 国狭槌尊 ー 豊斟渟尊 ー 泥土煮尊・沙土煮尊 ー 大戸之道尊・大苫辺尊 ー 面足尊・惶根尊 ー 伊弉諾尊・伊弉冉尊
意富斗能地神・大斗乃弁神共に「古事記」、「日本書紀」の両方に出現する神であり、共に神代七代と呼ばれる神々の五柱目に出現した神として描かれています。
- 意富斗能地神 = 「偉大な門にいる男性」という意
- 意富は「大」の美称。
- 斗は「門・戸」の意
- 地は男性の親称
- 大斗乃弁神 = 「偉大な門にいる女性」という意
- 大はそのまま「大」
- 斗は「門・戸」の意
- 弁は女性の親称
神名からわかる様に集落の門であったり家屋の戸が神格化した神であるといえます。
先代で集落の範囲や宅地の範囲を示す「杙」が神格した角杙神・活杙神が神格化して、次に門、戸が神格化した意富斗能地神・大斗乃弁神が神格化したという事は、ここで家屋などが造られたという事になるかと思います。
古事記では
古事記では「角杙神・活杙神」の次に出現する神で、「次意富斗能地神。次妹大斗乃辨神。(此二神名亦以音。)」と書かれています。現代語訳にすると「次にお生まれになった神の名は、意富斗能地神といい、その次生まれたには女神で妹大斗乃辨神といった。」と訳すことができます。この神も、他の今まで古事記で登場してきた神々と同様もお生まれになてすぐ姿を隠され(見えなくされ)、これ以降登場してきません。
日本書記では
日本書紀では、「次有神 大戸之道尊 一云 大戸之邊 大苫邊尊 亦曰大戸摩彥尊 大戸摩姬尊 亦曰大富道尊 大富邊尊」と記されています。現代語訳すれば「次に現れた神は、大戸之道尊話(一説には、大戸之邊)と大苫邊尊(または一説に、大戸摩彥尊と大戸摩姫尊、または大富道尊と大富邊尊)と云う。」となります。ほぼ古事記と同様の内容となっていますが、それぞれの神の別称が紹介されています。
神々のデータ
意富斗能地神
| 神祇 | 天津神、神世七代 |
| 神名 | 古事記 :意富斗能地神 日本書紀:大戸之道尊 |
| 神名の意味 | 偉大な門にいる男性 |
| 別称 | 大戸之邊、大戸摩彥尊、大富道尊 |
| 親 | ー |
| 小 | ー |
大斗乃弁神
| 神祇 | 天津神、神世七代 |
| 神名 | 古事記 :大斗乃弁神 日本書紀:大苫邊尊 |
| 神名の意味 | 偉大な門にいる女性 |
| 別称 | 大戸摩姬尊、大富邊尊 |
| 親 | ー |
| 小 | ー |
意富斗能地神・大斗乃弁神を祀る神社
現在の所、当サイトでは、意富斗能地神・大斗乃弁神を主祭神とする神社の紹介記事はありません。
まとめ
意富斗能地神・大斗乃弁神は男女対偶神として出現しており、両神を一代として数えています。その神名から門または戸の守護神と考えられ祀られてきたとされる一方で、先に説明した通り「地」は男性を、「弁」は女性を示すと考えられる事から「斗」は身体に性を持った男女神の顕現を表すとする説もあるなど、神名をどのように解釈するかで大きくその本質が変わってしまいそうな神であると言えます。