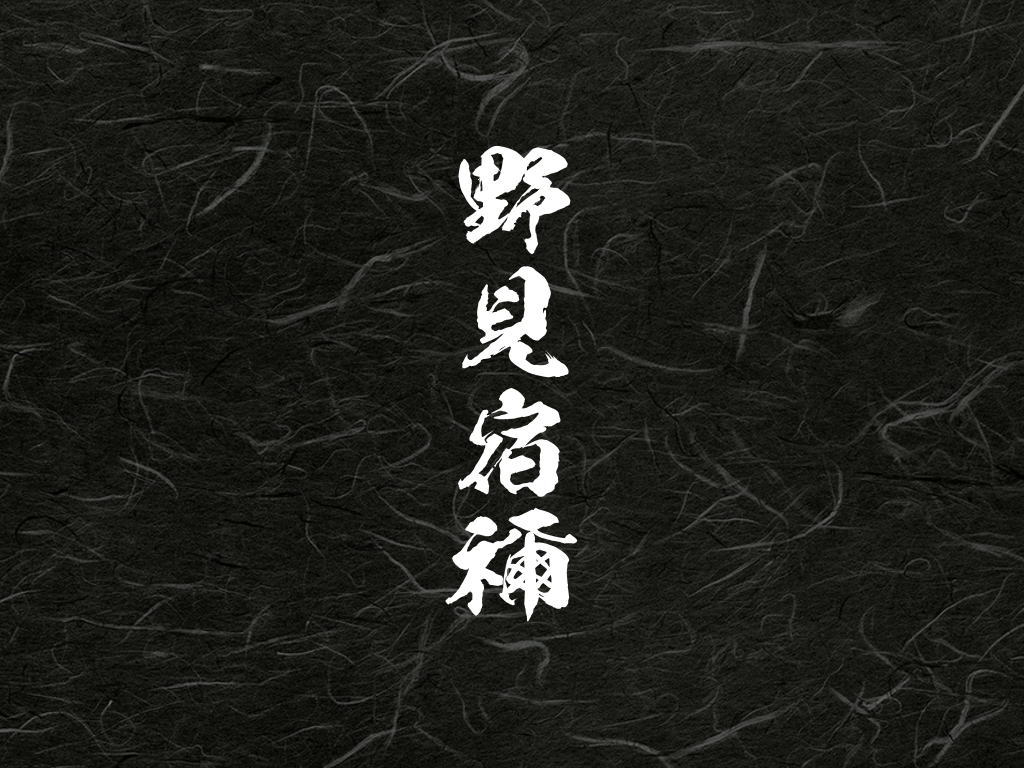野見宿禰とは?
記紀での出現状況
- 日本書紀に出現
- 巻第六、垂仁天皇の段に登場
(垂仁天皇)七年秋七月己巳朔乙亥、左右奏言「當麻邑、有勇悍士、曰當摩蹶速。其爲人也、强力以能毀角申鉤、恆語衆中曰『於四方求之、豈有比我力者乎。何遇强力者而不期死生、頓得爭力焉。』」天皇聞之、詔群卿曰「朕聞、當摩蹶速者天下之力士也。若有比此人耶。」一臣進言「臣聞、出雲國有勇士、曰野見宿禰。試召是人、欲當于蹶速。」卽日、遣倭直祖長尾市、喚野見宿禰。於是、野見宿禰、自出雲至。則當摩蹶速與野見宿禰令捔力。二人相對立、各舉足相蹶、則蹶折當摩蹶速之脇骨、亦蹈折其腰而殺之。故、奪當摩蹶速之地、悉賜野見宿禰。是以、其邑有腰折田之緣也。野見宿禰乃留仕焉。
(垂仁天皇)三十二年秋七月甲戌朔己卯、皇后日葉酢媛命一云、日葉酢根命也薨。臨葬有日焉、天皇詔群卿曰「從死之道、前知不可。今此行之葬、奈之爲何。」於是、野見宿禰進曰「夫君王陵墓、埋立生人、是不良也、豈得傳後葉乎。願今將議便事而奏之。」則遣使者、喚上出雲國之土部壹佰人、自領土部等、取埴以造作人・馬及種種物形、獻于天皇曰「自今以後、以是土物更易生人樹於陵墓、爲後葉之法則。」天皇、於是大喜之、詔野見宿禰曰「汝之便議、寔洽朕心。」則其土物、始立于日葉酢媛命之墓。仍號是土物謂埴輪、亦名立物也。仍下令曰「自今以後、陵墓必樹是土物、無傷人焉。」天皇、厚賞野見宿禰之功、亦賜鍛地、卽任土部職、因改本姓謂土部臣。是土部連等、主天皇喪葬之緣也、所謂野見宿禰、是土部連等之始祖也。
第十一代垂仁天皇によって出雲国より呼び寄せられ、そのまま京に滞在する事になったという人物になります。呼び出される切っ掛けとなった「当麻蹶速」との力比べになる訳ですが、この力比べが相撲の原点であるとして相撲の神として知られています。しかし、日本書紀で書かれている内容は、相撲というよりキックボクシングの様な感じで双方蹴りあい、最終的に野見宿禰は当麻蹶速の脇骨を折り、また腰を折って殺してしまっています。これが相撲の発祥とすると、元々相撲というのは「蹴り」もありだったのでしょうか。
野見宿禰は、力比べにより当麻蹶速の領地をそのまま与えられ、都周辺に居を構えたとされ、垂仁天皇32年に再び日本書紀に登場します。この時は、有力者が亡くなった時の殉死をどうするかという内容でした。
当時は時の権力者が亡くなった時、殉死した家臣などを同時に埋葬する風習があったとされます。この殉死について、強制的なのか自発的なのかで意味合いがかなりかわってきそうですが、「殉死を禁止した」という文言が垂仁天皇の代で登場してい来ることか、強制的な殉死(要は殺害した)は禁止したということなのでしょう。卑弥呼の埋葬の時は、100人以上を殉死(殺すというより生き埋めか?)させたと言われていますね。
野見宿禰は自らの一族の拠点である出雲国に使いを送り、「埴輪」を造り垂仁天皇に献上したと記されています。この埴輪を殉死の代わりにしたとして、垂仁天皇から「土師職」を賜り、本姓を改めて土師臣としたとしています。これにより、天皇の埋葬は土師連が取り仕切った由縁になっています。ただ、葬儀の際火葬が一般化してくると、土師氏の権力も衰退していったようです。
神々のデータ
| 神祇 | 人神 |
| 神名 | 日本書紀:野見宿禰 |
| 役職 | 土師職 |
| 先祖 | 天穂日命 |
| 子 | 土師阿多勝 子孫は、後に大江氏、菅原氏、秋篠氏を称する。 特に、菅原氏からは菅原道真を輩出する。 |
| 系図 | 天穂日命 ┃ 建比良鳥命 ┃ (略) ┃ 甘美乾飯根命 ┃ 野見宿祢 |
野見宿禰を祀る神社
- 野見神社(式内社・郷社)
愛知県豊田市野見山町4-21- 豊田市中心部を流れる矢作川の左岸沿いにある野見山の山頂に鎮座する神社。境内には相撲の神である野見宿禰を祀る神社らしく「土俵」が設置されています。