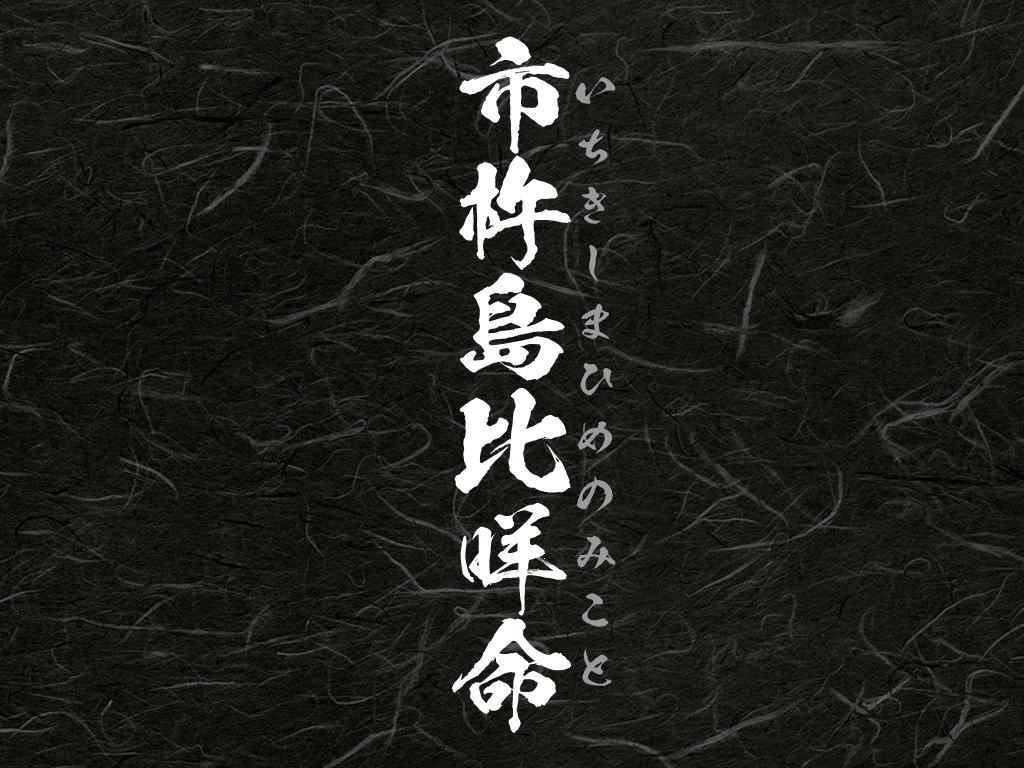市杵島比咩命とは?
登場文献
- 古事記
- 上つ巻「天の安の河の誓約」の段
故爾各中置天安河而。宇氣布時。天照大御神。先乞度建速須佐之男命所佩十拳劔。打折三段而。奴那登母母由良邇。〈此八字以音。下效此。〉振滌天之眞名井而。佐賀美邇迦美而。〈自佐下六字以音。下效此。〉於吹棄氣吹之狹霧所成神御名。多紀理毘賣命。〈此神名以音。〉亦御名謂奧津嶋比賣命。次市寸嶋〈上〉比賣命。亦御名謂狹依毘賣命。次多岐都比賣命。〈三柱。此神名以音。
- 日本書紀
- 神代上「天照大御神と素盞嗚尊との誓約」の段
於是天照大神乃索取素戔鳴尊十握劒,打折爲三段,濯於天眞名井,𪗾然咀嚼〈𪗾然咀嚼,此云佐我彌爾加武。〉而吹棄氣噴之狹霧〈吹棄氣噴之狹霧,此云浮枳于都屢伊浮岐能佐擬理。〉所生神,號曰田心姬;次湍津姬;次市杵嶋姬。凡三女矣。
市杵島比咩命の伝承
「伊邪那岐神」は黄泉の国から戻り禊を行った時に、三貴子をお産みになりました。
- 高天原の統治を命じられた「天照大御神」
- 夜の統治を命じられた「月読命」
- 海の統治を命じられた「建速須佐之男命」
しかし、建速須佐之男命は母である伊邪那美命に会いたいとして海の統治を行わず泣いてばかりいたので、伊邪那岐神より根の国(黄泉の国)に行くがいいと追放されてしまいます。建速須佐之男命は根の国に向かう前に、天照大御神に在ってから向かおうとして高天原に向かいます。
建速須佐之男命が高天原に近づくと、山川が響動し国土が皆震動した為、天照大御神は建速須佐之男命が高天原を奪いに来たとして武装して建速須佐之男命を迎えた。
高天原を奪いに来たとする天照大御神と、根の国に向かう前に会いに来たとする建速須佐之男命。
「どうしたら建速須佐之男命の潔白が証明できるだろうか」の問いに、建速須佐之男命は「誓約を行って子どもを生みましょう。」と答えています。
そこで、天照大御神は建速須佐之男命が腰に刷いていた十拳劔を受け取ると、三つに砕いてバリバリと嚙み砕き、フゥーと吐き出すと、多紀理毘売、市杵島比売、多岐都比売の三女神がお生まれになった。
ポイント
この時生まれた多紀理毘売命、市杵島比売命、多岐都比売命の三女神を祀られている神社から「宗像三女神」と呼ばれています。北九州から当選半島にかけての玄界灘の海上交通の安全を祈願する神として、それぞれの三柱が沖津宮に多紀理毘売命、中津宮に多岐都比売命、辺津宮に市杵島比売命が祀られていて、島それぞれが御神体とされています。
宗像三女神はヤマト朝廷が北九州などを勢力圏に取り込む以前の豪族などに信仰されていた神ではであり、ヤマト朝廷が北九州などを支配下に収めると朝鮮半島、その先の大陸の関係が非常に重要になっていき、ヤマト朝廷最高神である天照大御神との関係が構築されていったと思われます。朝鮮半島や大陸との外交については朝廷が直接行っていた事を示しているのかもしれませんね、
弁才天との習合
ヒンズー教のサラスヴァティーが仏教に取り入れられ弁才天と呼ばれる様になり、それが日本に伝わって神仏習合の中で「市杵島比咩命」と同一視される様になっていきます。
元々水に関連する神であったサラスヴァティーと、水の神とされる市杵島比咩命が同一視される訳ですから、当然水に関連する神として祀られていて、「弁天堂」というと水辺に建っているイメージがあるかと思います。また、神社の境内社に辨天社などが建てられている場合、社の周囲を掘って水が溜まる様にしていて水に浮かぶ社の様な雰囲気にしている所も多々あるかと思います。
明治になって神仏分離が行われると、大半の弁天社は祭神を市杵島比咩命を祀る神社を選択した所が大多数だったようです。この余波は、江戸期に設けられた七福神霊場に現れていて、弁才天の札所が市杵島比咩命を祀っている神社となっている所がある辺りに感じられるかと思います。
神々のデータ
| 神名 | 市杵島比咩命 |
| 神祇 | 天津神 |
| 別称 | 謂狹依毘賣命 |
| 親 | 天照大御神、建速須佐之男命 |
| 配偶 | ー |
| 子 | ー |
| 備考 |
市杵島比咩命を祀る神社
- 胸形社
- 豊田市平戸橋町波岩一
延喜式式内社 加茂郡 灰宝神社
-

-
胸形社(愛知県豊田市平戸橋町)延喜式内社論社
続きを見る
-
- 豊田市平戸橋町波岩一
- 馬場瀬神社
- 豊田市平戸橋町馬場瀬三九番地六八
延喜式式内社 加茂郡 灰宝神社
-

-
馬場瀬神社(愛知県豊田市平戸橋町)延喜式内社論社
続きを見る
-
- 豊田市平戸橋町馬場瀬三九番地六八
まとめ
七福神の弁財天と同一視されたことにより、実は非常になじみ深い神様なのが「市杵島比咩命」になります。いつしか、弁才天が弁財天と才→財と変わっていき、財についての神様としても信仰されるようになっていますね。お金を洗うと御神徳が宿るという「銭洗い弁財天」が全国各地にあるのも特徴の一つかと思います。