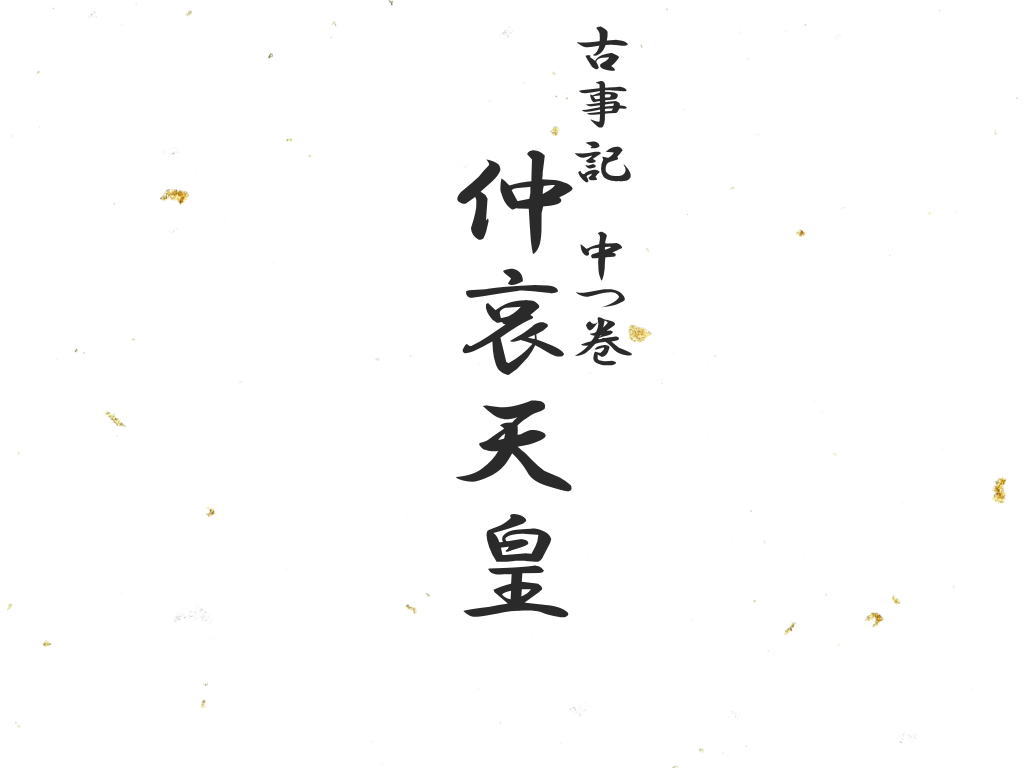香坂王・忍熊王の反逆
後に応神天皇となる御子「宇美」の出産を無事終えた神功皇后は、筑紫国の巡回を行ったのか、筑紫国末羅縣において岩の上でアユを釣っています。古事記が編纂された当時、この末羅縣で女性がアユを釣っていた行事が神功皇后と結びついたのかなと思います。
御子の宇美がある程度大きくなるのを待っていたか、もしくは出産直後だったのかはその時期は書かれていないので判断しようがないのですが、神功皇后はついにヤマト朝廷の本国である「大和国」への帰還を行う事になります。
古事記を読む
於是、息長帶日賣命、於倭還上之時、因疑人心、一具喪船、御子載其喪船、先令言漏之「御子既崩。」如此上幸之時、香坂王・忍熊王聞而、思將待取、進出於斗賀野、爲宇氣比獦也。爾香坂王、騰坐歷木而是、大怒猪出、堀其歷木、卽咋食其香坂王。其弟忍熊王、不畏其態、興軍待向之時、赴喪船將攻空船。爾自其喪船下軍相戰。
此時忍熊王、以難波吉師部之祖・伊佐比宿禰爲將軍、太子御方者、以丸邇臣之祖・難波根子建振熊命爲將軍。故追退到山代之時、還立、各不退相戰。爾建振熊命、權而令云「息長帶日賣命者既崩。故、無可更戰。」卽絶弓絃、欺陽歸服。於是、其將軍既信詐、弭弓藏兵。爾自頂髮中、採出設弦(一名云宇佐由豆留)、更張追擊。故、逃退逢坂、對立亦戰。爾追迫敗於沙沙那美、悉斬其軍。於是、其忍熊王與伊佐比宿禰、共被追迫、乘船浮海歌曰、
伊奢阿藝 布流玖麻賀 伊多弖淤波受波 邇本杼理能 阿布美能宇美邇 迦豆岐勢那和
卽入海共死也。
- 息長帶日賣命は神功皇后
- 喪船とは棺を載せる船
- 斗賀野は大阪市北区兎我野町附近とされるが、神戸市灘区を流れる都賀川流域とる説も存在する。
- 宇氣比獦とは誓約狩りの意で吉凶を占う為に行う狩りの事
- 山代は山城国
- 設弦は予備の弓弦の事
- 逢坂は京都府と滋賀県の境にある逢坂山
- ここで出てくる海は琵琶湖をさす
現代語訳
さて、神功皇后は大和国に帰還しようとする時に、なにやら神功皇后と御子に対する反乱が起こる可能性を感じとったので、喪船を一艘用意して、御子をこの喪船に乗せて、まず
「御子はすでに崩御なされた。」
という噂を流された。
いよいよ神功皇后が大和国へ向かって進軍し始めると、香坂王・忍熊王はこの噂を聞き、皇后を捕えようと斗賀野に進出して「誓約狩り」を行った。
香坂王は、クヌギの木に登っていると、大きな怒り狂った猪が現れ、(香坂王が登っている)クヌギの木の根元を掘って倒してしまい、、たちまちに香坂王に喰らいつき食べてしまった。
弟である忍熊王は兄が猪に食い殺されてしまうといいう凶兆を目にしながらも、恐れることなく軍勢を率いて皇后を待ち構えていた時、喪船が到着した時、忍熊王はこの棺が載っていない空船を攻めようとした。皇后はこの喪船より軍勢を下船させて、戦闘となった。
この時、忍熊王は難波吉師部の先祖である伊佐比宿祢を将軍とし、皇太子は丸邇臣の先祖となる難波根子建振熊命を将軍とされた。
皇太子軍は忍熊王の軍勢を山代まで追い詰めるが、この地にて軍勢を立て直した忍熊王軍と一進一退の戦いとなっていきます。
建振熊命は計略を用いて、
「神功皇后は既に崩御なされた。だから、もはや戦う必要はなくなった。」
と言い、弓弦を断ち切り、偽りの降伏(武装解除)を行った。
忍熊王方の伊佐比宿祢将軍は、この偽りの降伏を信じてしまい、弓から弦を外して兵を引いてしまいます。すると皇太子方は髪の毛の中に隠し持っていた弓弦を張り直し、追撃を行った。この追撃により、忍熊王方は逢坂まで退いて、そこで再び軍を立て直し立ち向かった。
しかし、太子軍は追撃の手を緩めず、沙々那美にて打ち破り、忍熊王方は壊滅した。忍熊王と伊佐比宿祢は追い詰められ、船に乗り琵琶湖の湖上にて
「伊奢阿藝 布流玖麻賀 伊多弖淤波受波 邇本杼理能 阿布美能宇美邇 迦豆岐勢那和」
と歌を詠み、そのそまま琵琶湖に入水し、二人とも亡くなってしまった。
まとめ
古代日本では、末子相続が基本でした。応神天皇も仲哀天皇の末子なので、順当に考えれば皇位継承第一位が応神天皇になるわけですが、やはりこの辺りがうまく動いているのは、末子がある程度大きくなり皇太子などに就いていた場合(周囲の臣下もそれを認めている、)に限った場合なのではと思う訳です。
応神天皇の場合、父である仲哀天皇は生まれる前に崩御されてしまっており、さらに、出産は都がある大和国から遠く離れた筑紫国。しかも、神功皇后は仲哀天皇に従い筑紫国居ましたが、香坂王・忍熊王を生んだ大中津比売命(紀:大中姫)は記載はない物の仲哀天皇の行幸には従わず、大和国に居たと考えられます。
仲哀天皇が皇太子を決めずに崩御した。皇后と生まれた御子は都から遠く離れた筑紫国にいる。こんな状況で末子相続はうまくいくなんてまったく想像できない訳です。だから、異母兄である香坂王と忍熊王はまだ見ぬ御子への皇位相続を認めなかった為、武力衝突(跡目争い)が起きたんだろうと思います。