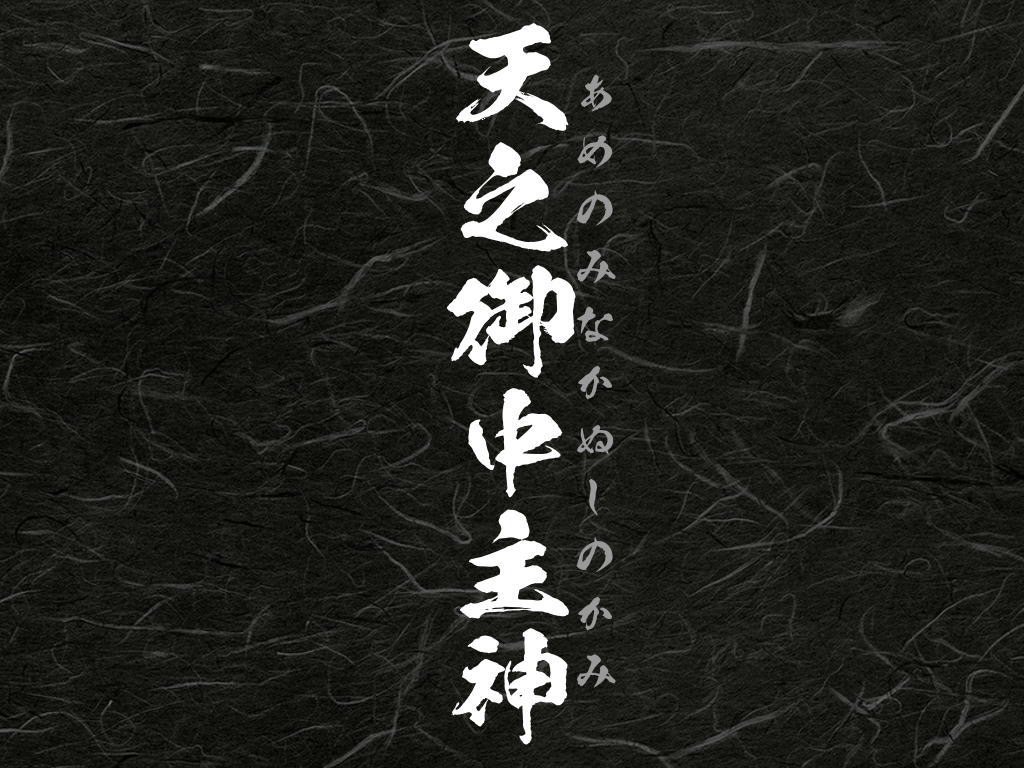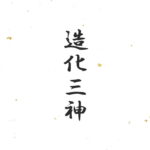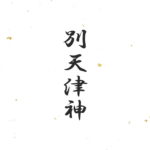天之御中主神とは?
記紀での出現状況
- 古事記に出現
天と地が始まった時に一番最初に出現した神- 神名:天之御中主神
天地初發之時、於高天原成神名、天之御中主神(訓高下天、云阿麻。下效此、)次高御產巢日神、次神產巢日神。此三柱神者、並獨神成坐而、隱身也。
- 日本書紀に出現
本文では出現せず、第四別伝にて出現した神- 神名:天御中主尊
一書曰、天地初判、始有倶生之神、號國常立尊、次國狹槌尊。又曰、高天原所生神名、曰天御中主尊、次高皇産靈尊、次神皇産靈尊。皇産靈、此云美武須毗。
古事記では、天と地が分かれた時に、一番初めに出現した神であると記されており、後に出現した高御産巣日神と神産巣日神を合わせた三柱の神の総称である「造化三神」の一柱であり、宇摩志阿斯訶備比古遲神、天之常立神を合わせた五柱による「別天津神」の一柱でもあります。
『古事記』の冒頭に「天地初めて発りし時に、高天の原に成りませる神の名は、天之御中主の神、次に、高御産巣日の神、次に、神産巣日の神。この三柱の神は、みな独神と成りまして、身を隠したまひき。」 とあるように、天と地が分かれた時に天(高天原)に出現した一番最初の神を「天之御中主の神」と記されています。
もう一方の歴史書である『日本書紀』では、天地開闢の本文にはその名を見る事はできず、いくつか併記されているいくつかの一書の中の一つに登場するのみとなっていて、「天御中主尊」と記されています。
古事記、日本書紀共に、天之御中主神が登場するのはこの部分のみとなっています。
天之御中主神は何を示している神なのか?
その神名から「高天原の神聖な中央に位置する主君」という意を示しているのではないかと考えられています。
天之御中主神が出現した時の「天」はとてつもなく大きな空間が広がってだけだと考えられ、これから高天原として発展していく「天」の中心を指し示すことを表した神なのではないでしょうか。何か物事を始める時に必ず中心点となる一点を決めてそこから肉付けをしていくと思いますが、この中心点こそが「天之御中主神」であると想像してもらえるとわかりやすいかと思います。
そんな天之御中主神が鎌倉時代以降、(伊勢)神宮の外宮の神職である「渡会氏」よって提唱された「伊勢神道」によって、外宮の御祭神である「豊受大神」と同一視されるようになっていきます。この辺りは、平安以前の「仏主神従」の神仏習合から「神主仏従」の考えが生まれ始め、さらに神宮における内宮と外宮の勢力争いなど様々な要因が絡み合って、一番最初に出現した神と豊受大神を同一視する事によって、ある種の絶対神的な存在にしようとしたと考えられています。
神々のデータ
| 神祇 | 天津神、造化三神、別天津神 |
| 神名 | 古事記 :天之御中主神 日本書紀:天御中主尊 |
| 別称 | ー |
| 親 | ー |
| 子 | ー |
天之御中主神を祀る神社
- 石座神社
鎮座地:愛知県新城市大宮字狐塚十四番地
延喜式内社:宝飯郡 石座神社
-

-
石座神社(愛知県新城市大宮)延喜式内社
続きを見る
-
まとめ
天之御中主神を「高天原の中心の主となる神」と単純に訳していいのかは、古事記や日本書記に置いて出現した時にその名を見るだけで、以降の活動については見られない神となります。この事から、登場する事に意味がる神であると考えられ、まさに「天の中心となった神」と見る事ができるのかなと。
この「天の中心にいる神」と天体の中心と考えられた「北極星」信仰などと習合していき、妙見信仰に繋がっていったそうです。